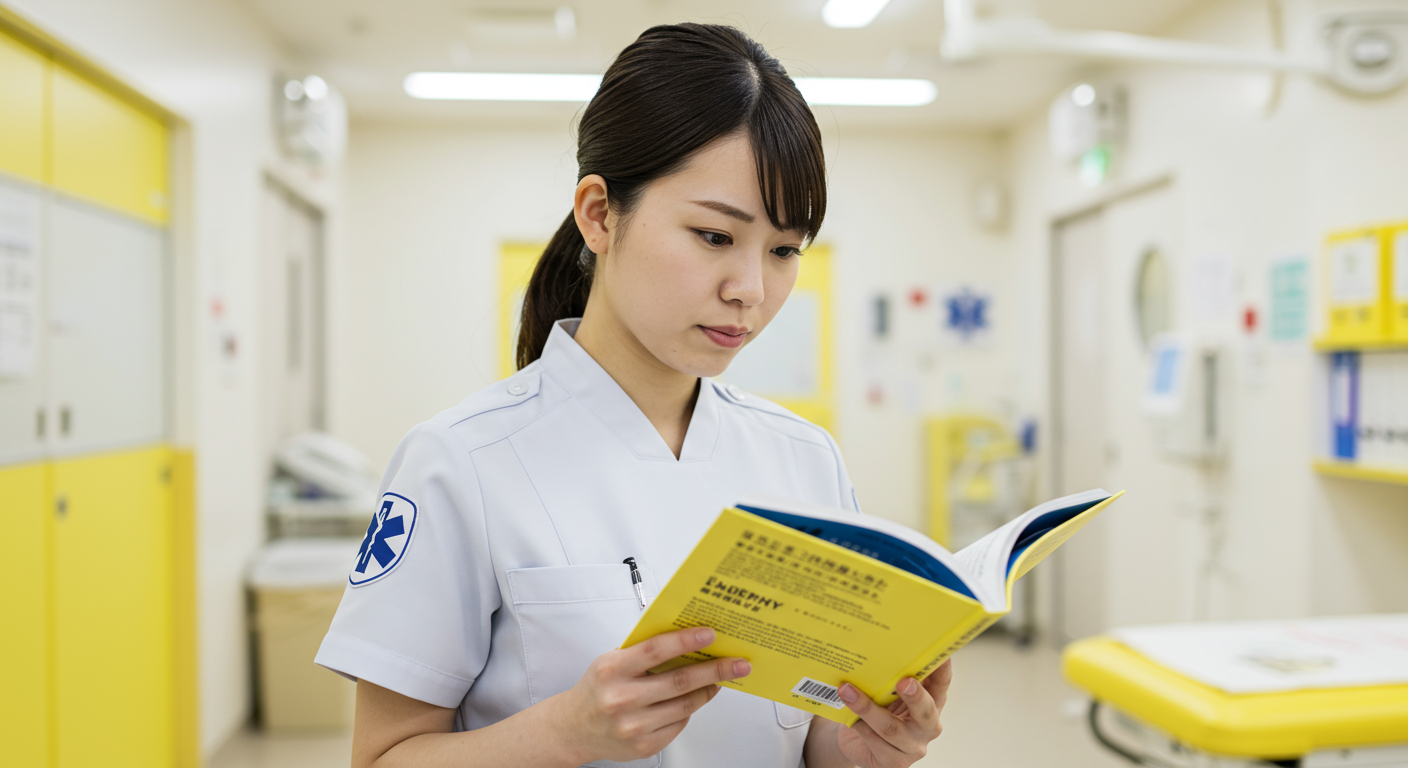1. 生命倫理とは?
〇生命倫理(バイオエシックス)とは、医療や生命科学の進歩に伴い発生する倫理的な課題を考察する学問です。救急救命士は、緊急時に患者の命を救う使命を担っているため、生命倫理の基本を理解し、適切な判断を下すことが求められます。
2. 生命倫理の4原則
〇生命倫理には、以下の4原則が基本としてあります。救急救命士として活動する際にも重要な指針となります。
① 自律尊重の原則(患者の意思を尊重する)
〇患者の自己決定権を尊重することが重要です。ただし、救急現場では意識がない患者も多く、事前の意思確認が難しい場合があります。そのため、家族の意向や事前指示書(リビングウィル) などを参考にする必要があります。
② 善行の原則(患者にとって最善の利益を考える)
〇救急救命士は、患者の命を救うために最善の行動を取るべきです。しかし、すべての処置が患者にとって有益とは限りません。
例えば・・・
・心肺停止の状態で輸血しないと助からないから輸血したい医療側(善行の原則)と
・宗教上の理由で輸血をさせたくない傷病者(患者)側の家族(自立尊重の原則)のパターンです。
※救急救命士が輸血することはありませんが、それに近い処置を行います。
家族に説明し同意を得るか、オンラインMCに指導助言を得るなどの判断が求められます。
③ 無危害の原則(患者に害を及ぼさない)
〇医療行為には必ずリスクが伴います。救急救命士の処置が患者の利益を損なわないよう、安全性を最優先に考える必要があります。特に、救急救命処置の適応外の行為や、自己の技量を超えた処置を行わないよう注意が必要です。
④ 正義の原則(公平性を保つ)
〇限られた医療資源を公平に分配することも生命倫理の重要なポイントです。例えば、大規模災害時におけるトリアージ(治療の優先順位の決定) では、個々の患者の利益と社会全体の利益を天秤にかける判断が求められます。
3. 救急救命士が直面する生命倫理の課題
ケース①:DNAR(蘇生拒否)の対応
〇救急現場では、「心肺蘇生を望まない」という患者の意向(DNAR:Do Not Attempt Resuscitation) に遭遇することがあります。しかし、事前指示が明確でない場合や、家族の意見が分かれる場合には、救急救命士として適切な判断をする必要があります。
「ポイント」
① DNAR指示が正式な書面で確認できるか?
②家族や医療機関と連携し、患者の最善の利益を考慮する
ケース②:本人の意思が確認できない場合の処置
〇救急隊が到着した時点で、患者が意識を失っており、医療処置の意思確認ができないケースは多くあります。このような場合、基本的には「患者の最善の利益を考え、救命を優先する」ことになります。
「ポイント」
①意識のない患者には、通常の救急処置を適用(推定的同意)
②可能であれば家族や関係者に確認し、方針を調整
4. 国家試験対策問題
問題1
生命倫理の四原則に関する記述のうち、誤っているもの を選べ。
A. 自律尊重の原則とは、患者が自らの医療行為を決定する権利を尊重することである。
B. 善行の原則とは、患者に対して最大限の利益を提供することである。
C. 無危害の原則とは、医療従事者が患者の安全を第一に考え、有害な行為を避けることである。
D. 正義の原則とは、治療は常に救急搬送順に提供されるべきである。
解答:D
解説:
正義の原則では、治療の順番は公平性や緊急性に基づいて決定されるため、「救急搬送順」とは限らない。トリアージなどの判断が求められる場面もある。
まとめ
〇救急救命士は、医療技術だけでなく、生命倫理に基づいた判断力も求められます。患者の権利を尊重しながら、最善の医療を提供する という意識を持ち、日々の業務に取り組むことが重要です。国家試験では生命倫理に関する問題も出題されるため、基本原則をしっかり押さえておきましょう!