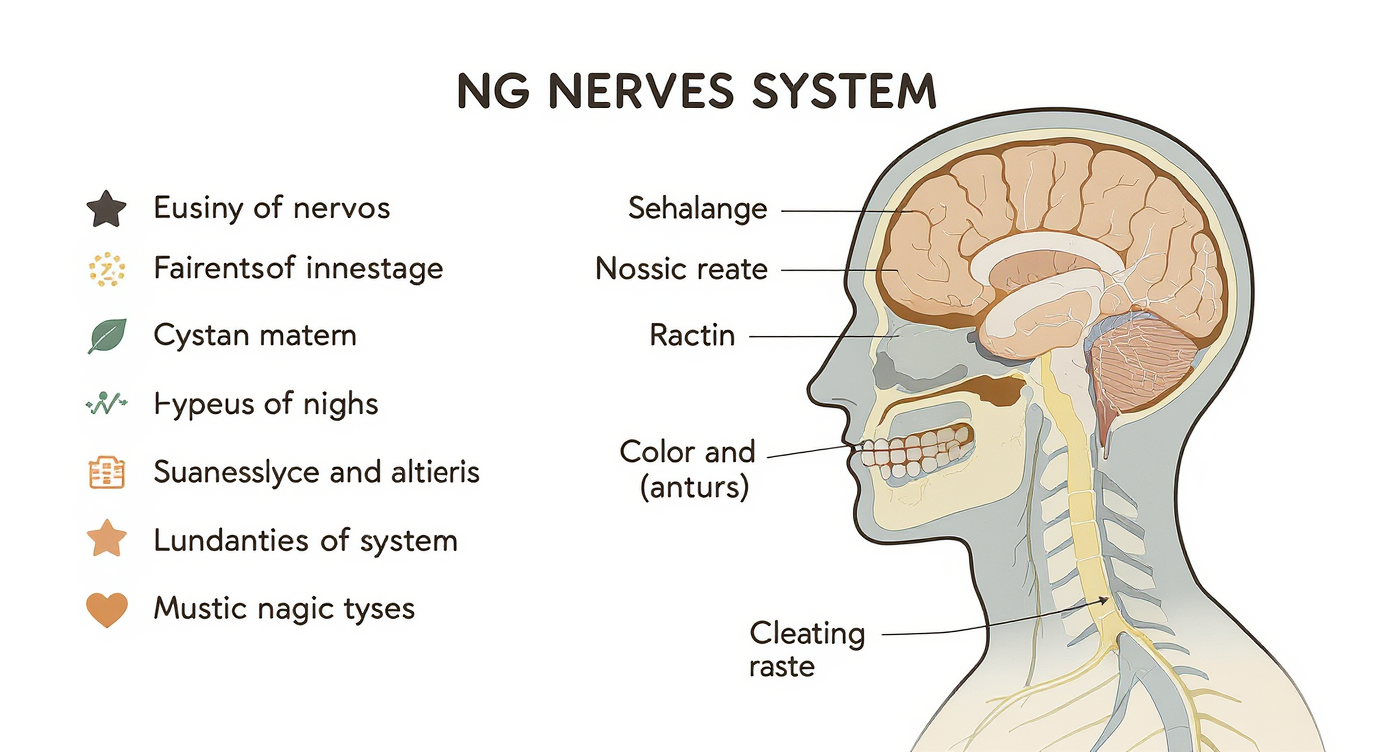【はじめに】
神経を知ることは、“人間を知ること”だ**
人が涙を流すのも、怒りを覚えるのも、
走り出したくなるのも、心が折れそうになるのも、
すべては 神経系が作る“反応の物語” だ。
救急の現場では、たった1分で
「この人は今、何が起きているのか?」
を見抜かなければならない。
その判断の9割は 神経系の知識 を土台にしている。
- 意識がない
- 右半身が動かない
- 瞳孔が開いている
- 呼吸が乱れている
- 言葉がおかしい
これらの“わずかな変化”の裏にある真実を読み解くために、
神経系の理解は 救急・医療・一般の健康理解の中心 に位置する。
この記事は、
一般読者が読んでも理解できるやさしさと、
国家試験受験生が読めば得点できる深さ
を両立して書き上げた“魂の記事”だ。
※本記事で扱うテーマは、救急搬送全体の基本となる
ボディメカニクスの考え方と密接に関係しています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶ 救急搬送の基本となるボディメカニクス
腰を守って傷病者も守る!ボディメカニクス完全ガイド — TETSU十郎/救急救命士/防災士
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【救急救命士国家試験対策】緊急安静搬送と意識障害を極める!一次性と二次性脳病変の違いを見抜け!
📚 神経系を理解するためのおすすめ書籍(Amazon対応版)
-
① 『運動・からだ図解 脳・神経のしくみ 新版』(石浦章一 著)
👉 脳・神経のしくみを豊富な図解で解説した超わかりやすい入門書。
一般読者でも理解できる「やさしく・正確・視覚的」な構成で、神経系の基本理解に最適。- 脳・神経の構造と働きをイラストで把握できる
- 救急・看護・リハビリ・一般読者まで幅広く対応
- 国家試験の土台づくりにも使える
-
② 『神経理学療法学(標準理学療法学 専門分野)』(奈良 勲 著)
👉 中枢神経疾患(脳卒中・脳外傷・脊髄損傷など)に対する理学療法を専門的に学べる一冊。
神経系の臨床応用を深めたい医療者・PT学生向けの標準テキスト。- 脳卒中の病態・評価・リハアプローチが深く理解できる
- 中枢神経の障害像が体系立てて学べる
- 国家試験・臨床どちらにも役立つ内容
-
③ 『クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる!』(相澤 純也 著)
👉 神経系疾患を「理学療法」という視点で“具体的にどう考えるか”を解説した良書。
評価 → 仮説 → 治療選択 という臨床推論が身につく構成。- 神経系リハの思考プロセスを具体的に学べる
- 脳卒中・パーキンソン病などの臨床像を深く理解
- 医療者の“考える力”を鍛える実践書
神経系の基礎~臨床応用まで体系的に学べる厳選の3冊です。
1. 神経系とは何か──身体を動かし、心をつくり、命を守る『究極のネットワーク』
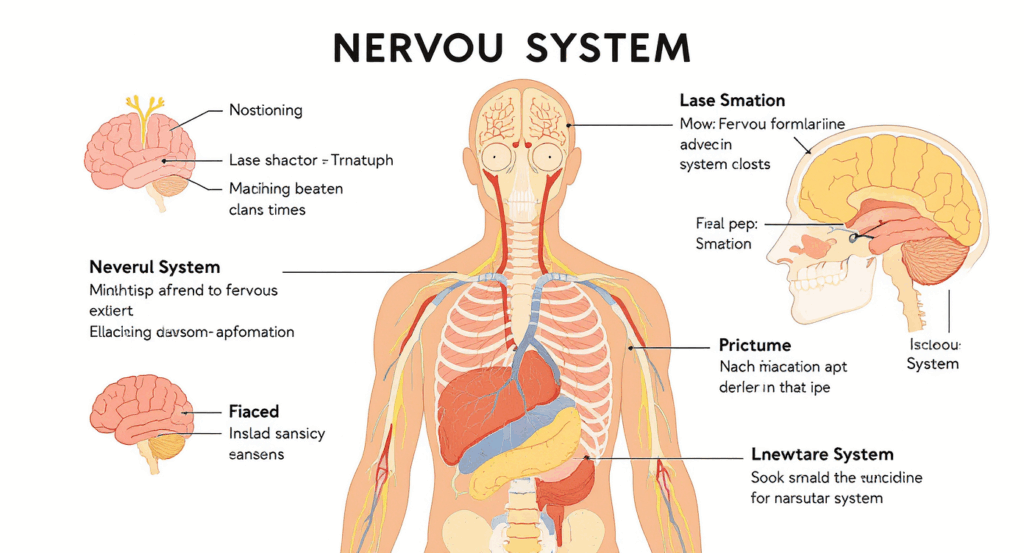
神経系を一言でまとめると、
人間のすべての情報を受け取り、処理し、応答する統合システム
具体的には次の3つの仕事をしている。
- 感じる(感覚)
痛い・熱い・寒い・触られた・音がする・光を見る…すべて神経。 - 考える・記憶する・判断する(中枢)
脳の働き。感情も思考も神経の活動。 - 動かす(運動)
筋肉に「動け」と命令を送るのも神経。
つまり神経系は、
“心”と“体”と“命”のすべてを創り出す中心装置 だ。
2. 神経系の分類──中枢神経と末梢神経の役割
■ 中枢神経(CNS:Central Nervous System)
脳と脊髄。
ここは“人間の中枢サーバー”だ。
● 大脳
- 思考
- 感情
- 言語
- 記憶
- 運動指令
人間らしさの源。
国家試験では「前頭葉=運動」「後頭葉=視覚」が頻出。
● 小脳
- バランス
- 筋肉の微調整
- 運動のスムーズさ
酔ったときにまっすぐ歩けないのは小脳が乱れるから。
● 脳幹
- 呼吸
- 心拍
- 意識
- 生命維持装置の中心
脳幹が障害されると生命に直結する。
● 脊髄
脳と身体をつなぐ“高速道路”。
損傷すると 損傷部位より下が動かない。
救急で最重要。
■ 末梢神経(PNS:Peripheral Nervous System)
● 体性神経
- 痛み
- 温度
- 触覚
- 位置感覚
- 随意運動(自分の意思で動かす動き)
転倒時の“しびれ”“麻痺”の評価はここ。
● 自律神経
- 交感神経(戦うモード)
- 副交感神経(休むモード)
人間は一生、この2つのバランスで生きている。
3. 自律神経のしくみ──“心と体のアップダウン”を生む二つの神様
■ 交感神経(Fight / Flight)
危険・緊張・ストレス時に働く。
- 心拍 ↑
- 血圧 ↑
- 気管支拡張
- 瞳孔散大
- 発汗 ↑
救急現場で患者の脈が速いのは“ショック”だけではない。
恐怖や不安も交感神経を強烈に刺激する。
■ 副交感神経(Rest / Digest)
安心・休息・食事のときに働く。
- 心拍 ↓
- 消化促進
- 瞳孔収縮
- 体が緩む
寝る前に眠くなるのは、ここが働いているから。
4. ニューロン(神経細胞)──“心が伝わる”電気と化学の仕組み
国家試験の頻出テーマ。
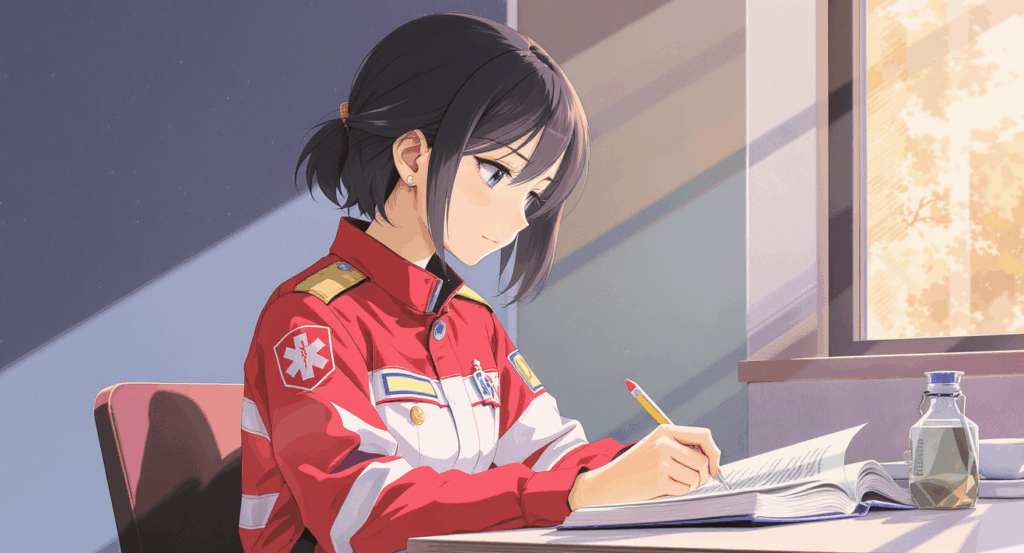
神経は電気で情報を伝える。
しかし、神経と神経の間(シナプス)は“化学物質”で伝わる。
■ ニューロンの構造
- 樹状突起:情報を受け取る
- 細胞体:判断する
- 軸索:情報を送る
■ シナプス
神経伝達物質で情報を送る。
代表的なのは、
- アセチルコリン
- ノルアドレナリン
- セロトニン
- GABA
これらは感情・記憶・運動・ストレス反応すべてに関与する。
つまり、
“気持ちの変化” も “身体の反応” も、同じ仕組みで繋がっている。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【救急救命士国家試験対策】緊急安静搬送と意識障害を極める!一次性と二次性脳病変の違いを見抜け!
📚 神経系を理解するためのおすすめ書籍(Amazon対応版)
-
① 『運動・からだ図解 脳・神経のしくみ 新版』(石浦章一 著)
👉 脳・神経のしくみを豊富な図解で解説した超わかりやすい入門書。
一般読者でも理解できる「やさしく・正確・視覚的」な構成で、神経系の基本理解に最適。- 脳・神経の構造と働きをイラストで把握できる
- 救急・看護・リハビリ・一般読者まで幅広く対応
- 国家試験の土台づくりにも使える
-
② 『神経理学療法学(標準理学療法学 専門分野)』(奈良 勲 著)
👉 中枢神経疾患(脳卒中・脳外傷・脊髄損傷など)に対する理学療法を専門的に学べる一冊。
神経系の臨床応用を深めたい医療者・PT学生向けの標準テキスト。- 脳卒中の病態・評価・リハアプローチが深く理解できる
- 中枢神経の障害像が体系立てて学べる
- 国家試験・臨床どちらにも役立つ内容
-
③ 『クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる!』(相澤 純也 著)
👉 神経系疾患を「理学療法」という視点で“具体的にどう考えるか”を解説した良書。
評価 → 仮説 → 治療選択 という臨床推論が身につく構成。- 神経系リハの思考プロセスを具体的に学べる
- 脳卒中・パーキンソン病などの臨床像を深く理解
- 医療者の“考える力”を鍛える実践書
神経系の基礎~臨床応用まで体系的に学べる厳選の3冊です。
5. 救急現場と国家試験で重要な「神経系の異常」
■ ① 脳卒中
- 片麻痺
- ろれつ不良
- 顔面麻痺
- 視野欠損
- 激しい頭痛(SAH)
- 意識障害
FASTは必須:Face / Arm / Speech / Time
■ ② てんかん
- 突然のけいれん
- 意識消失
- その後のもうろう
発作後の「ポストイグタル状態」を理解していないと誤判断の危険。
■ ③ 末梢神経障害
- 手足のしびれ
- 顔面神経麻痺
- 感覚鈍麻
脳卒中との鑑別は国家試験の鉄板。
■ ④ 意識障害(JCS・GCS)
神経学の最重要評価。
- 呼びかけに応じない
- 痛み刺激で動くか
- 何点か
これはまさに神経系の評価そのもの。
6. 国家試験で得点するための「神経系のコアポイント」
✔ 大脳の働き(前頭葉=運動、後頭葉=視覚)
✔ 交感神経・副交感神経の違い
✔ ニューロンの構造
✔ シナプス伝達
✔ 脳幹=生命維持中枢
✔ 脊髄損傷の部位と症状
✔ 脳神経の代表的機能
✔ 脳卒中の症状とFAST
これは全部、
出題頻度トップクラスの“取りこぼせない領域”。
7. まとめ──神経を学ぶほど、人を理解できる
神経系を知ることは、

- 患者の苦しみ
- 感情の動き
- 行動の理由
- 症状の背景
これらを理解することにつながる。
この記事を読み終えたあなたは、
ただ「知識を覚えた」のではなく、
“人の変化を読み解く力”
“国家試験を突破する力”
両方を手に入れている。
神経系は難しいと言われるが、
本当は“人間らしさの核心”だからこそ面白い。
※本記事で扱うテーマは、救急搬送全体の基本となる
ボディメカニクスの考え方と密接に関係しています。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
▶ 救急搬送の基本となるボディメカニクス
腰を守って傷病者も守る!ボディメカニクス完全ガイド — TETSU十郎/救急救命士/防災士
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【救急救命士国家試験対策】緊急安静搬送と意識障害を極める!一次性と二次性脳病変の違いを見抜け!
📚 神経系を理解するためのおすすめ書籍(Amazon対応版)
-
① 『運動・からだ図解 脳・神経のしくみ 新版』(石浦章一 著)
👉 脳・神経のしくみを豊富な図解で解説した超わかりやすい入門書。
一般読者でも理解できる「やさしく・正確・視覚的」な構成で、神経系の基本理解に最適。- 脳・神経の構造と働きをイラストで把握できる
- 救急・看護・リハビリ・一般読者まで幅広く対応
- 国家試験の土台づくりにも使える
-
② 『神経理学療法学(標準理学療法学 専門分野)』(奈良 勲 著)
👉 中枢神経疾患(脳卒中・脳外傷・脊髄損傷など)に対する理学療法を専門的に学べる一冊。
神経系の臨床応用を深めたい医療者・PT学生向けの標準テキスト。- 脳卒中の病態・評価・リハアプローチが深く理解できる
- 中枢神経の障害像が体系立てて学べる
- 国家試験・臨床どちらにも役立つ内容
-
③ 『クリニカルリーズニングで神経系の理学療法に強くなる!』(相澤 純也 著)
👉 神経系疾患を「理学療法」という視点で“具体的にどう考えるか”を解説した良書。
評価 → 仮説 → 治療選択 という臨床推論が身につく構成。- 神経系リハの思考プロセスを具体的に学べる
- 脳卒中・パーキンソン病などの臨床像を深く理解
- 医療者の“考える力”を鍛える実践書
神経系の基礎~臨床応用まで体系的に学べる厳選の3冊です。