◆はじめに
2024年12月2日から、日本の医療保険制度は大きく変わりはじめています。
Yahoo!ニュースなどでも「マイナ保険証がないと10割負担になる」といった見出しが並び、多くの人が不安になりました。
Yahoo!記事はこちら👉【12月2日から】「マイナ保険証」がないと“10割負担”になると聞き焦り! 友人は「切り替えなくても3割負担だよ」と言っていましたが、どういうことでしょうか?“3つの対処法”を確認(ファイナンシャルフィールド) #Yahooニュース
実際、医療機関で働く人からも
「患者さんが受付で混乱してトラブルになりやすい」
「保険証が使えなかったと言われる事例が増えている」
といった声も聞こえてきます。
しかし結論から先に言うと――
マイナ保険証がなくても、原則として10割負担にはなりません。
多くの人はこれまでどおり 3割負担(年齢等で1~2割の人も)で受診できます。
では、なぜ「10割負担」という話が広がったのでしょうか?
このブログでは、
- 誤解が生まれた背景
- 何がどう変わるのか
- 実際に気をつけたいこと
- 12月2日以降に安心して受診するための“3つの対処法”を一般向けにやさしく解説していきます。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【やさしく解説】生活保護制度とは?
📚参考図書(救急救命士・医療学生におすすめ)
-
『救急救命士標準テキスト 改訂第11版』へるす出版
国家試験対策の定番。酸素飽和度・換気・循環評価など、モニタリングの基本が体系的に学べます。
➡️ Amazonで見る -
『イラストで解る 救急救命士国家試験直前ドリル 第4版』
国試過去問と出題傾向を分析したドリル。
➡️ Amazonで見る -
病気がみえる vol.5 血液 第3版
文字より“ビジュアル”で覚える。血液疾患の理解が劇的に変わる1冊。
➡️ Amazonで見る -
『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン2022〔第6版〕』日本呼吸器学会
呼吸生理と酸素療法の最新知見を網羅。慢性呼吸不全や在宅酸素療法を理解するうえで必読の一冊。
➡️ Amazonで見る
◆1. そもそも「マイナ保険証」とは?
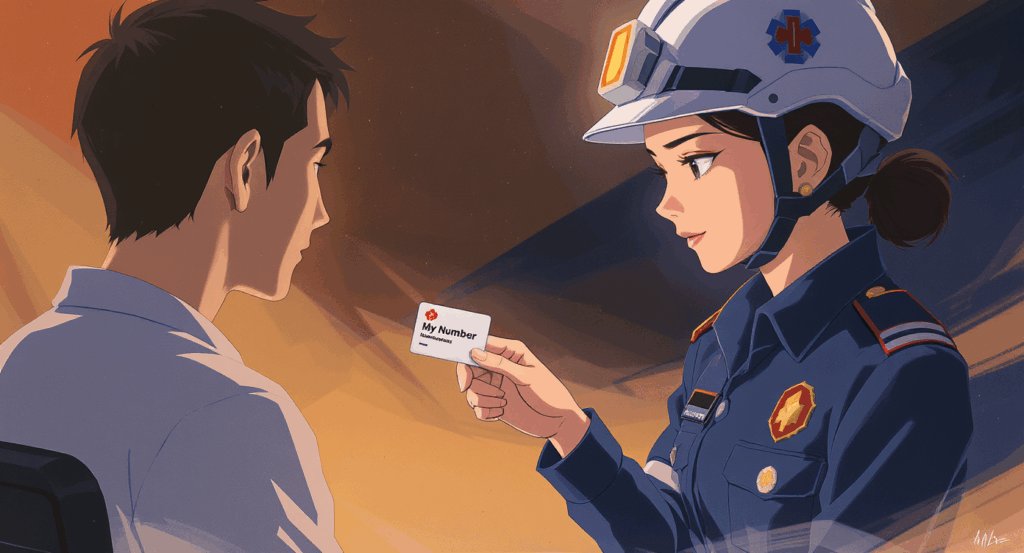
●1-1 マイナンバーカードを保険証として使う仕組み
「マイナ保険証」とは、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようにした仕組みのこと。
これにより、医療機関の受付でカードをかざすだけで「保険資格」がオンラインで確認できます。
●1-2 何のために導入されたの?
主な目的は以下の通りです。
- 保険証の更新・管理の簡略化
- 医療機関での受付の効率化
- 過去の薬剤情報・健診情報を共有してより良い医療を提供
- 偽造防止などセキュリティの強化
特に薬剤情報の連携は医師・薬剤師にとってメリットが大きく、重複処方や危険な飲み合わせを防ぐ効果が期待されています。
●1-3 紙の保険証はどうなる?
2024年12月2日から、紙の保険証の新規発行が停止されました。
ただし現在手元にある保険証はすぐに無効になるわけではなく、有効期限までは使用可能です。
保険者によっては「2025年12月1日まで有効」と案内されているところもあります。
◆2. なぜ「10割負担になる」という話が広まったのか?
●2-1 そもそも10割負担とは何か
健康保険証が確認できない場合、医療機関は「保険適用できるか不明」になります。
そのため、
- いったん10割全額を支払い
- 後日保険証を確認して差額が返金される
という運用が昔から存在します。
●2-2 制度移行期に“確認エラー”が多発
オンライン資格確認の導入直後、医療機関で次のようなトラブルが多発しています。
- カードリーダーが患者のマイナンバーカードを読み込まない
- ネットワークエラーで保険資格を確認できない
- 保険者(会社・国保)側の登録が追いついていない
このような場合、受付側は「保険が適用できるか確証が持てない」ため、
誤って10割を請求してしまうケースが報告されています。
全国調査では、実際にこうした事例が 1000件を超える との報告もあります。
●2-3 しかし厚生労働省は「10割にはならない」と明言
厚労省は広報資料の中で、明確に次のように述べています。
マイナ保険証が読み取れない・使えない場合であっても、
医療費が10割負担になることはない。
つまり、制度上は「必ず保険診療として扱うバックアップ手続き」が用意されているということ。
ではなぜ現場では10割請求が起きているのか?
理由は単純で、
- 新制度が始まったばかり
- 医療機関の運用が統一されていない
- 一部の医療機関で対応マニュアルが整っていない
という“移行期特有の混乱”です。
◆3. 友人が言っていた「切り替えなくても3割負担」の意味
あなたの友人の
「切り替えなくても3割負担だよ」
は正しいです。
理由は:
- 保険証が有効である限り
- マイナ保険証に切り替えていなくても
- 本人が健康保険に加入しているのが確実なら
通常どおり3割負担で受診できる からです。
つまり、
- マイナ保険証が必須なのではなく
- “保険資格が確認できるかどうか”が重要
ということです。
◆4. 実際に困るのはこういう時:受診トラブル例
制度上は3割負担で受診できますが、現場では次のようなケースでトラブルが起こります。
●4-1 保険証の有効期限切れ
期限切れだと医療機関は保険資格を確認できず、10割対応になることがあります。
●4-2 転職直後・扶養変更直後
保険者が変わると、オンライン資格確認のデータが反映されるまで数日~数週間かかることがあります。
●4-3 マイナ保険証の読み取りエラー
制度移行直後は多く発生しています。
●4-4 国保の滞納
滞納していると「特別療養費扱い」となり、窓口10割→後日請求という形になります。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【やさしく解説】生活保護制度とは?
📚参考図書(救急救命士・医療学生におすすめ)
-
『救急救命士標準テキスト 改訂第11版』へるす出版
国家試験対策の定番。酸素飽和度・換気・循環評価など、モニタリングの基本が体系的に学べます。
➡️ Amazonで見る -
『イラストで解る 救急救命士国家試験直前ドリル 第4版』
国試過去問と出題傾向を分析したドリル。
➡️ Amazonで見る -
病気がみえる vol.5 血液 第3版
文字より“ビジュアル”で覚える。血液疾患の理解が劇的に変わる1冊。
➡️ Amazonで見る -
『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン2022〔第6版〕』日本呼吸器学会
呼吸生理と酸素療法の最新知見を網羅。慢性呼吸不全や在宅酸素療法を理解するうえで必読の一冊。
➡️ Amazonで見る
◆5. 不安なら絶対にやっておきたい“3つの対処法”
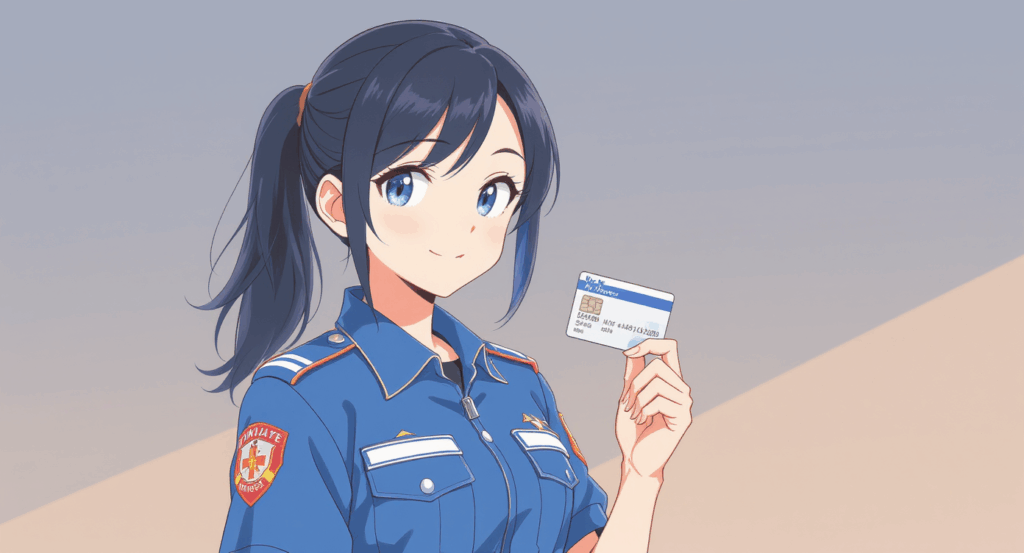
ここからが一番重要な部分です。
12月2日以降、トラブルを避けるために守ってほしい対処法を整理します。
◆対処法①
マイナンバーカードがない人は「資格確認書」を持っておく
マイナンバーカードを持っていない人でも、
資格確認書を使えば保険証と同じように受診できます。
- 申請不要で交付される場合が多い
- 無料
- マイナ保険証を使わない人のための代替手段
つまり、
紙の保険証 → 資格確認書 → マイナ保険証
という3段構えのどれかを持っていればOK。
◆対処法②
マイナ保険証登録済の人は「読み取りエラー時の対応」を知っておく
受付で次のように伝えれば安心です:
- 「保険証利用登録済です」
- 「読み取りできない場合は申立書で確認ができます」
オンライン資格確認がエラーでも、
- 過去の受診履歴
- 資格申立書
- 保険証番号の照会
など複数の確認ルートがあるため、
10割負担にはなりません。
◆対処法③
保険資格に変化があった人は必ず確認する
特に以下の人は注意が必要です:
- 転職した
- 扶養に入った/外れた
- 国保から社保に変わった
- 国保の滞納がある
- 住所変更した
資格情報の反映が遅れると、
受付で“無資格”と判定される場合があります。
◆6. よくある質問(Q&A)
●Q1:マイナ保険証に切り替えないとダメなの?
A:義務ではありません。資格確認書でも受診できます。
●Q2:10割請求された場合は?
A:後日、保険者に手続きすれば保険分が返還されます。
●Q3:マイナ保険証のメリットは?
A:薬剤情報の共有、受付の効率化、高額療養費の手続き簡略化など。
◆7. 救急隊として感じる「現場のリアル」
救急隊として患者搬送に関わる立場からも、この制度変更は無関係ではありません。
●搬送先の受付で“エラー”が起こると処理が遅れる
特に救急患者の受付では、
「保険証が見つからない」
「マイナカードを忘れた」
「読み込めない」
といった事例は非常に多いです。
●制度が不安定な時期は“確認作業が増える”
受付スタッフの負担が増え、医療機関内の流れが遅くなる可能性もあります。
読者に伝えたいのは、
「制度が不完全な状態で始まっている」ということを理解し、余裕を持って受診してほしい
というメッセージです。
◆8. 【まとめ】12月2日以降も焦らなくて大丈夫

最後にこの記事の要点をまとめます。
✔ マイナ保険証がなくても10割負担にはならない
✔ 多くの人はこれまで通り3割負担で受診できる
✔ ただし移行期の“確認エラー”で10割請求が発生することもある
✔ 資格確認書 or マイナ保険証 or 有効な紙保険証があれば大丈夫
✔ 保険資格が変わった人は絶対に要チェック
✔ 不安なら3つの対処法で確実に回避できる
そして何より大切なのは、
不安を煽る情報だけを見て慌てるのではなく、
正しい制度の仕組みを理解すること。
この記事が、受診の不安を少しでも取り除く手助けになれば嬉しいです。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【やさしく解説】生活保護制度とは?
📚参考図書(救急救命士・医療学生におすすめ)
-
『救急救命士標準テキスト 改訂第11版』へるす出版
国家試験対策の定番。酸素飽和度・換気・循環評価など、モニタリングの基本が体系的に学べます。
➡️ Amazonで見る -
『イラストで解る 救急救命士国家試験直前ドリル 第4版』
国試過去問と出題傾向を分析したドリル。
➡️ Amazonで見る -
病気がみえる vol.5 血液 第3版
文字より“ビジュアル”で覚える。血液疾患の理解が劇的に変わる1冊。
➡️ Amazonで見る -
『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン2022〔第6版〕』日本呼吸器学会
呼吸生理と酸素療法の最新知見を網羅。慢性呼吸不全や在宅酸素療法を理解するうえで必読の一冊。
➡️ Amazonで見る


