こんにちは。今回はプロ野球選手山本由伸選手のトレーニング法をお手本にして、国家試験(特に救急救命士試験など)を目指すあなたの“勉強スタイル”に置き換えてみたいと思います。優しい口調で、読んでいて「なるほど自分にもできそう」と思えるように書きました。
🚑 救急救命士国家試験・学習教材おすすめ
国家試験対策から現場応用まで、“救急救命士”を目指す方・指導する方のための教材を紹介します。
-
救急救命士標準テキスト
国家試験出題基準に対応した“基礎から専門分野まで”を網羅する決定版。救急救命士を学ぶ全ての人の「土台」となる教材です。 -
必修 救急救命士国家試験対策問題集2025 これだけやれば大丈夫!
過去5年分の国家試験を整理・解説。ジャンル別・A〜D問題別に分類されており、効率的な演習が可能です。 -
救急救命士国家試験対策Deru-Q 2026
要点整理に特化した正文集。忙しい時期の「最終確認・覚え直し」に最適な1冊です。 -
救急救命士国家試験対策〇×問題集 2026年版
○×形式で軽く演習できるタイプ。通勤・隙間時間など、「スキマ学習」にぴったりです。 -
EMT Crash Course(英語版)
国際的視点や英語文献への慣れに最適。英語対応や海外資格を視野に入れる方におすすめです。 -
救急救命士国家試験対策〇×問題集2025
前年版ですが、演習量を増やしたい方にコスパ良く使える併用教材です。
🛠 学習を深めるヒント
- テキストを「読む」より「つくる」:章末まとめを自分で図解・カード化すると理解が定着します。
- 間違いの振り返り:問題集は“なぜ間違えたか”を書き出して次に活かしましょう。
- 反復教材を活用:Deru-Qや〇×問題集は、通勤・休憩時間の“繰り返し”用に。
- 模試形式の練習:本番同様に時間を計り、“試験モード”の集中力を養う。
- 気分転換教材を1冊:語呂・イラスト系参考書を加えて「継続しやすい環境」をつくる。
はじめに:なぜ山本選手のトレーニングが勉強に活きるのか?
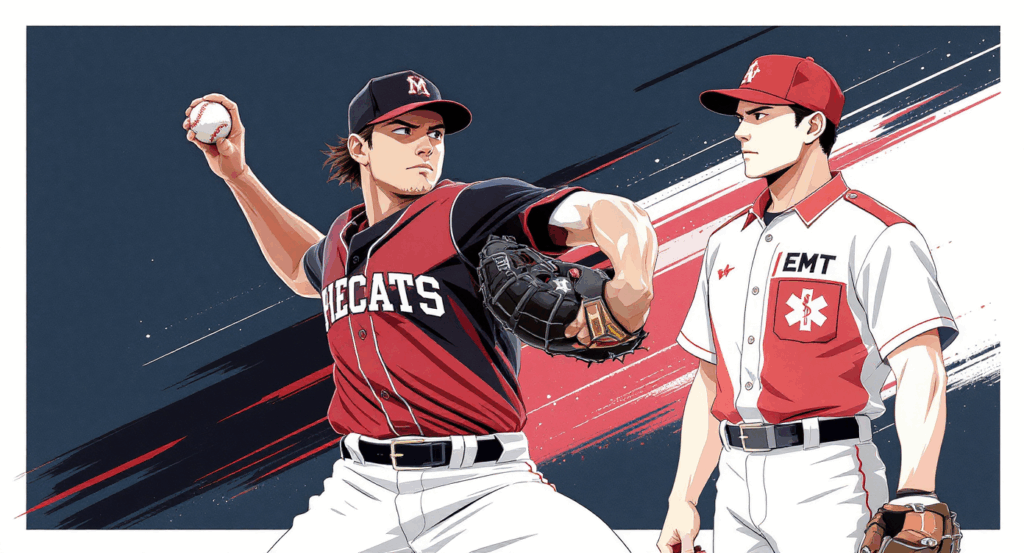
山本選手は、決して「ただ筋肉を増やせば強くなる」というパターンではなく、体の使い方・可動域・体幹・習慣・連動性を重視しています。
この考え方を勉強に応用すると、単なる“量をこなす”よりも「知識をどう使えるようにするか」「どう自分のスタイルに落とし込むか」がとても大事になります。
ですので、ここでは山本選手が行っている実際のトレーニングメニュー3つと、それを“勉強に活かす対応メニュー3つ”をご紹介します。
1.山本選手のトレーニングメニュー
以下は山本選手が実際に取り入れているトレーニング、またその意図・効果が報じられているものです。勉強側に対応させるヒントとしても活用できます。
(1) 「ブリッジ」など体幹・可動域を高めるエクササイズ
山本選手はブリッジを日常的に取り入れています。肩甲骨や背骨、股関節の可動域を広げ、投球動作において下半身→体幹→上半身への力の伝達をスムーズにするためです。
例えば、「腹圧(腹腔内圧)が十分であると、体幹が“内側から膨らんだ柱”のようになり、力の伝達効率が上がる」といった指摘も。
ポイント
- 可動域を拡げる=動きの幅を増やす
- 体幹を安定させる=軸をつくる
- 動きを連動させる=“下から上へ、遠くから近くへ”という運動構造
(2) 「槍投げトレーニング」など運動連鎖を意識した動き
山本選手は、投球動作に似ている「槍投げ」のようなトレーニングも採り入れています。運動連鎖(下半身→体幹→上半身→腕)が強化され、肩甲骨の可動性・リリース感覚を磨くために利用されていると報じられています。
ポイント
- 全身を使った動き=“知識・理解・応用”に通じる
- 運動連鎖=“前段階→次段階”という流れを意識
- 似て非なる動きで刺激を入れる=“慣れ”を防ぐ
(3) 「ウェイトトレーニングをあえて減らす/質を重視」
興味深いのは、山本選手が通常の筋肥大を狙ったウェイトトレーニングをあまり重視しないという点。可動域・しなやかさ・機能的な筋力を重視するトレーニングアプローチをとっています。
筋肉量を増やすだけではなく、「その筋肉をどう使うか」「どこまで使えるか」を大切にしているということですね。
ポイント
- 量=ムダ、ではなく「使える量・使える質」
- 勉強に言い換えれば、“詰め込みすぎない”、“使える知識に変える”
2.対応メニュー:勉強に活かせる3つの実践ステップ
では、上記のトレーニングを“国家試験勉強”に落とし込んでいきましょう。勉強スタイルにそのまま使えるように、3つのステップを用意しました。
ステップ①:土台を整える「可動域・体幹」=『知識の軸』をつくる
ブリッジで体幹・可動域を整えるように、勉強でも 「知識の軸」をまずつくる 段階が必要です。
具体的には:
- 今日から「毎日10分だけ復習タイム」を設ける。昨日学んだ分野を読み返す。
- テキストを読んだあと、その章のポイントを1分で図に書いてみる。
- 自分が苦手と感じる用語・概念を抜き出して、“どこが軸なのか”を自分で整理する。
このように、知識を“使える土台”にしておくと、次の『演習・応用フェーズ』でブレにくくなります。山本選手の「軸を安定させる体幹トレーニング」と同じ意味合いです。
ステップ②:連動させる「全身運動」=『知識→理解→応用』をつなげる
槍投げトレーニングで全身を連動させる山本選手のように、勉強でも 「知識から理解、そして応用へ」を一連の流れにする ことがとても効果的です。
具体的に:
- テキストを読んで「知識を得る」→次に「どう使うか?」を問う(例:この知識はどんな場面で使うか?)
- 過去問や演習問題に挑戦し、「なぜこの選択肢?」を自分で説明してみる。
- 解いた後に「この問いのどこがポイントだったのか」「別の解き方はないか?」を図やフローチャートで書いてみる。
こうして “知識を動かす”(=理解)→“使える形にする”(=応用)という運動連鎖を作ることで、試験本番での対応力がぐっと高まります。
ステップ③:量より質、使える知識に変える=『機能的筋力』を目指す
山本選手が量よりも質・機能を重視しているように、勉強でも 「ただ詰め込む」ではなく「使える形に変える」 ことが合格を左右します。
具体的には:
- 過去問をただ500問解く、ではなく、間違えた10問にフォーカスして「なぜ間違えたか」「次はどう防ぐか」を吟味。
- テキストを読んだあと、「人に説明できるかどうか」でチェック。説明できなければ知識は“使えていない”と判断。
- 自分の言葉でノートを作る。辞書的・丸写し的でなく、「自分が理解した形」でまとめる。
このように“使える知識”をつくることで、試験本番、量に追われたときでも、落ち着いて力を発揮できるようになります。
3.具体の習慣化/週サイクルの提案
勉強を「トレーニング化」するためには、習慣化が鍵です。山本選手も毎日ルーティンを欠かしません。ここでは「1週間サイクル」のモデルを提案します。
| 曜日 | やること |
| 月曜 | 新しい分野のインプット(30〜45分)、その日の“目的”をノートに書く。 |
| 火曜 | 昨日のインプットを復習(10〜15分)、演習問題(1〜2問)+振り返り。 |
| 水曜 | 過去問演習(30分)、間違えた所の整理と“なぜ”をノートに。 |
| 木曜 | 集中しにくければ、軽めのテキスト読み+音読。/夜に10分だけ振り返り。 |
| 金曜 | 模擬的に時間を計って演習(60分)、解いた後の見直しを丁寧に。 |
| 土曜 | 苦手分野フォーカス(20〜30分)、友人や仲間と説明し合い。 |
| 日曜 | オフ+軽い復習(10分)+翌週の予定立て。休むのもトレーニングの一部。 |
このようなサイクルを“まずは1ヶ月”続けてみると、勉強のリズムができてきます。山本選手のように、体(ここでは“頭・知識”)が「この時間は勉強モード」と認識し始めるので、集中スイッチが入りやすくなります。
🚑 救急救命士国家試験・学習教材おすすめ
国家試験対策から現場応用まで、“救急救命士”を目指す方・指導する方のための教材を紹介します。
-
救急救命士標準テキスト
国家試験出題基準に対応した“基礎から専門分野まで”を網羅する決定版。救急救命士を学ぶ全ての人の「土台」となる教材です。 -
必修 救急救命士国家試験対策問題集2025 これだけやれば大丈夫!
過去5年分の国家試験を整理・解説。ジャンル別・A〜D問題別に分類されており、効率的な演習が可能です。 -
救急救命士国家試験対策Deru-Q 2026
要点整理に特化した正文集。忙しい時期の「最終確認・覚え直し」に最適な1冊です。 -
救急救命士国家試験対策〇×問題集 2026年版
○×形式で軽く演習できるタイプ。通勤・隙間時間など、「スキマ学習」にぴったりです。 -
EMT Crash Course(英語版)
国際的視点や英語文献への慣れに最適。英語対応や海外資格を視野に入れる方におすすめです。 -
救急救命士国家試験対策〇×問題集2025
前年版ですが、演習量を増やしたい方にコスパ良く使える併用教材です。
🛠 学習を深めるヒント
- テキストを「読む」より「つくる」:章末まとめを自分で図解・カード化すると理解が定着します。
- 間違いの振り返り:問題集は“なぜ間違えたか”を書き出して次に活かしましょう。
- 反復教材を活用:Deru-Qや〇×問題集は、通勤・休憩時間の“繰り返し”用に。
- 模試形式の練習:本番同様に時間を計り、“試験モード”の集中力を養う。
- 気分転換教材を1冊:語呂・イラスト系参考書を加えて「継続しやすい環境」をつくる。
4.注意点と補足:無理せず、自分を知ろう
- 山本選手も「無理なフォーム変更」「過剰な筋肥大」を避けています。勉強でも「一気に全部詰めよう」とすると、疲弊してしまいがちです。
- 自分に合わない勉強法でムリするのではなく、「自分のリズム・集中できる時間帯」を知ること。
- 量をこなす日はあっても、それが目的ではなく“質を高める日”が中心になるように。
- 休息もちゃんと取りましょう。頭も体も、オフがあってこそ次に活きます。
5.まとめ:山本由伸流 “鍛える勉強”をあなたへ
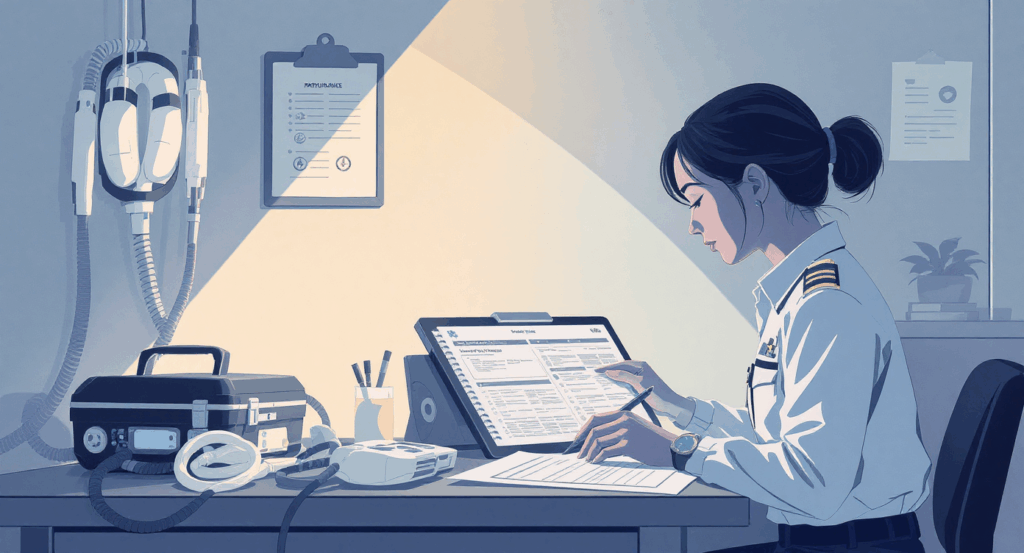
山本選手のトレーニング哲学を、勉強に置き換えると次のようになります
- 可動域・体幹を整える → 知識の軸をつくる
- 運動連鎖を意識する → 知識→理解→応用を流れにする
- 質を重視する → 使える知識に変える
- 習慣化・ルーティンを守る → 勉強を“当たり前”にする
- 無理せず継続する → 長期戦を勝つための精神
国家試験勉強は、マラソンのようなものです。派手な爆発力ではなく、淡々と続けられる力が最後に勝ちます。山本由伸選手が試合で見せる「安定感」「ブレないフォーム」「淡々と続ける姿」は、まさに試験勉強に通じるものです。
どうか自分のペースで、でも止まらず、今日も一歩。
「知識の軸を固める10分」「演習の1問」「振り返りノート」――これらを繋げていくことで、いつか大きな成果として現れます。
山本選手のように「動ける体」を作るように、自分の頭・知識・ペースを整えて。あなたの合格に向けて、応援しています!
🚑 救急救命士国家試験・学習教材おすすめ
国家試験対策から現場応用まで、“救急救命士”を目指す方・指導する方のための教材を紹介します。
-
救急救命士標準テキスト
国家試験出題基準に対応した“基礎から専門分野まで”を網羅する決定版。救急救命士を学ぶ全ての人の「土台」となる教材です。 -
必修 救急救命士国家試験対策問題集2025 これだけやれば大丈夫!
過去5年分の国家試験を整理・解説。ジャンル別・A〜D問題別に分類されており、効率的な演習が可能です。 -
救急救命士国家試験対策Deru-Q 2026
要点整理に特化した正文集。忙しい時期の「最終確認・覚え直し」に最適な1冊です。 -
救急救命士国家試験対策〇×問題集 2026年版
○×形式で軽く演習できるタイプ。通勤・隙間時間など、「スキマ学習」にぴったりです。 -
EMT Crash Course(英語版)
国際的視点や英語文献への慣れに最適。英語対応や海外資格を視野に入れる方におすすめです。 -
救急救命士国家試験対策〇×問題集2025
前年版ですが、演習量を増やしたい方にコスパ良く使える併用教材です。
🛠 学習を深めるヒント
- テキストを「読む」より「つくる」:章末まとめを自分で図解・カード化すると理解が定着します。
- 間違いの振り返り:問題集は“なぜ間違えたか”を書き出して次に活かしましょう。
- 反復教材を活用:Deru-Qや〇×問題集は、通勤・休憩時間の“繰り返し”用に。
- 模試形式の練習:本番同様に時間を計り、“試験モード”の集中力を養う。
- 気分転換教材を1冊:語呂・イラスト系参考書を加えて「継続しやすい環境」をつくる。


