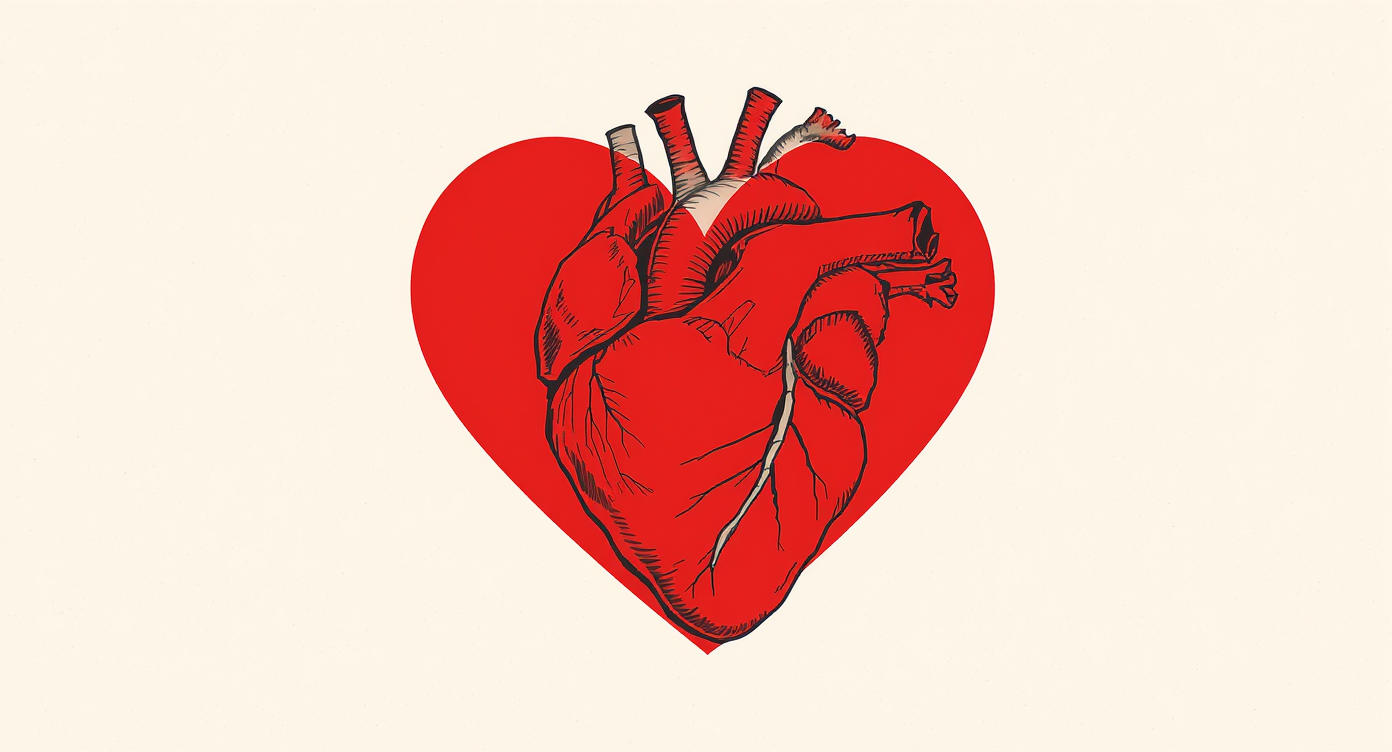心臓は24時間、一度も休むことなく動き続けています。その心臓の「電気仕掛けの発電所」の役割を担っているのが、右心房にある 洞結節(どうけっせつ) です。洞結節が正常に働くことで、心臓は規則正しいリズムで拍動しています。
しかし、この洞結節の働きが弱くなったり、止まったりしてしまう病気があります。それが 洞不全症候群(どうふぜんしょうこうぐん)/Sick Sinus Syndrome:SSS です。
この記事では、
医療従事者が読んでも正確で、一般読者にも理解しやすい ことを目指し、
洞不全症候群の基礎、原因、症状、検査、治療、日常生活、救急時のポイントまで詳しく解説します。
他にも記事が読みたい方はこちら👉心筋梗塞とは?──原因・症状・治療・予防をわかりやすく解説
■ 1. 洞不全症候群とは?
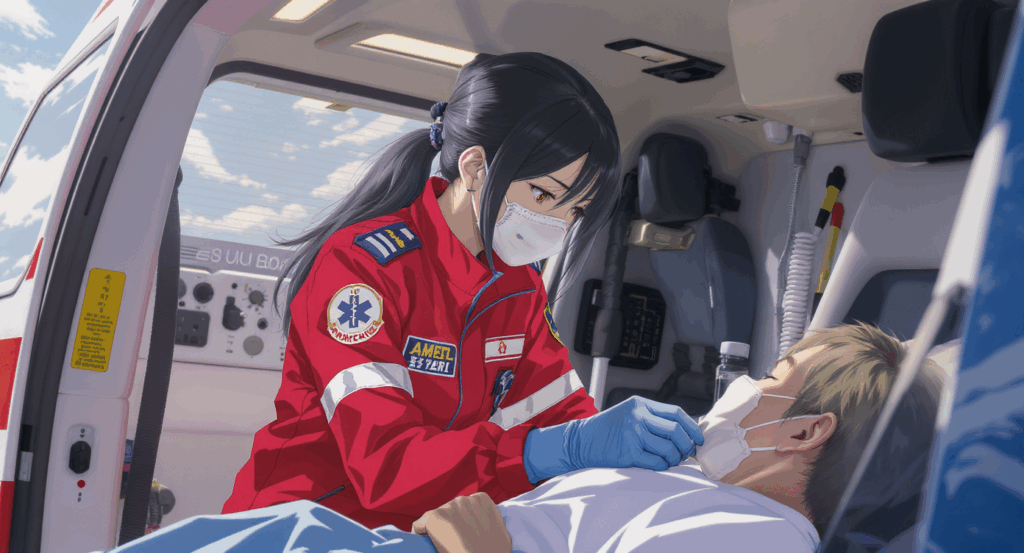
洞不全症候群とは、心臓のリズムを作り出す「洞結節」が適切に働かなくなることで、
脈が極端に遅くなったり、止まったり、リズムが不規則になる病気 です。
▼ 心臓のリズムの基本:洞結節の役割
心臓は「電気刺激」によって動いています。
洞結節 → 房室結節 → ヒス束 → プルキンエ線維
という順番で電気が伝わり、その結果「ドクン、ドクン」と拍動しています。
洞結節が指令を出せなくなると、心臓は“次の拍動”をどうしていいか分からず、
脈が遅くなる(徐脈)・脈が飛ぶ・停止する
という現象が起きます。
📚 心電図・不整脈の入門におすすめの書籍(Amazon対応版)
-
1. 『かげさんのイラストで学ぶ 心電図と不整脈めも』
👉 現役看護師「かげ」さんによる、イラスト多めの超入門書。
波形の“見え方”と“不整脈の理屈”がやさしく理解できます。
洞不全症候群など徐脈性不整脈の理解にもつながり、最初の一冊に最適。- 図が多く、心電図を学ぶハードルが下がる
- 不整脈の分類がやさしく整理されている
- 初めて心電図を読む人向けの構成
-
2. 『読み方だけは確実に身につく心電図』 (著:米山 喜平)
👉 心電図が苦手な人でも「読むコツ」から理解できる定番の入門書。
洞不全症候群(SSS)についても章内で触れており、徐脈理解の基礎固めに最適。- 心電図の読み方が段階的に理解できる
- SSSなど徐脈性不整脈の前段階の理解に使える
- 受験生・新人医療者の基礎固めに最適
-
3. 『不整脈 知って解消 不安と疑問』(別冊NHKきょうの健康)
👉 一般読者向けの入門書で、不整脈全体をやさしく整理した内容。
洞不全症候群カテゴリーにも触れている可能性が高く、“まず知りたい”に適した構成。- 読みやすく、一般家庭向けにも最適
- 不整脈の全体像がとても理解しやすい
- 患者説明用としても活用できる
洞不全症候群・徐脈性不整脈の基礎を学ぶ入門書として特におすすめの3冊です。
■ 2. なぜ洞不全症候群が起きるのか(原因)
洞結節の機能が低下する理由はいくつかあります。
① 加齢(最も多い原因)
洞結節も“臓器”のひとつであり、加齢によって細胞が弱ります。
60〜70代以上で発症しやすく、日本でも高齢化に伴い患者数が増えています。
② 心臓の病気
- 虚血性心疾患(心筋梗塞など)
- 心筋症
- 心膜炎
- 心臓手術後
これらは洞結節にダメージを与えることがあります。
③ 薬の影響
以下の薬は脈を抑える作用があり、洞不全を悪化させることがあります。
- β遮断薬
- Ca拮抗薬(特にジルチアゼム・ベラパミル)
- ジギタリス
- 抗不整脈薬
多くは高血圧や不整脈治療で使われています。
④ 自律神経の異常
迷走神経(副交感神経)が過剰に働くことで、洞結節の働きが低下することがあります。
若年者でもストレス、痛み、強い咳、嘔吐などで一時的に起きることがあります。
⑤ その他
- 甲状腺機能低下症
- 電解質異常
- 感染症
などが原因となることもあります。
■ 3. 症状:脈が遅くなるとどうなる?
洞不全症候群の症状は「脳への血流不足」によるものが中心です。
▼ よくみられる症状
- めまい・ふらつき
- 失神、意識を失う
- 動悸
- 息切れ
- 倦怠感
- 胸部の違和感
- 集中力の低下
- 突然倒れる(最も危険)
脈が極端に遅くなるほど、脳への血流が保てなくなり、
急に意識を失う危険性があります。
▼ 特徴的な現象:発作性の停止
洞不全症候群では、普通に生活している中で
急に数秒〜数十秒、脈が止まる ことがあります。
特に数秒以上止まると、目の前が真っ暗になったり倒れたりします。
■ 4. 洞不全症候群のタイプ(分類)
洞不全症候群は大きく3つに分類されます。
● ① 洞停止・洞房ブロック型
洞結節が指令を出さない、もしくは指令が心房に伝わらないタイプ。
脈が突然止まる のが特徴です。
ECGでは P波 が消失します。
● ② 洞徐脈型
洞結節は働くが、脈が全体的に遅くなる タイプ。
安静時の脈拍が40台・30台になる人もいます。
● ③ 徐脈‐頻脈症候群(最も有名)
“脈が遅い時と早い時が混ざる”タイプ。
▼ 具体例
- 普段は脈が遅い
- 突然、心房細動など頻脈発作が起きる
- また脈が遅くなる
脈がジェットコースターのように乱れ、症状も強く出やすいのが特徴です。
■ 5. どのように検査する?
① 心電図(ECG)
最も基本。
洞停止や徐脈が記録できれば確定につながります。
② ホルター心電図(24時間心電図)
1日の脈の動きを記録する検査。
発作が散発的に起きる人に有効です。
③ イベントレコーダー
1週間〜数週間、専用の心電計を装着して調べる方法。
“発作が月に数回しかない”人に有効。
④ 血液検査
甲状腺ホルモン・電解質など、他の病気の影響を確認します。
⑤ 運動負荷試験
運動しても脈が上がらない場合、洞結節機能の低下を疑います。
他にも記事が読みたい方はこちら👉心筋梗塞とは?──原因・症状・治療・予防をわかりやすく解説
📚 心電図・不整脈の入門におすすめの書籍(Amazon対応版)
-
1. 『かげさんのイラストで学ぶ 心電図と不整脈めも』
👉 現役看護師「かげ」さんによる、イラスト多めの超入門書。
波形の“見え方”と“不整脈の理屈”がやさしく理解できます。
洞不全症候群など徐脈性不整脈の理解にもつながり、最初の一冊に最適。- 図が多く、心電図を学ぶハードルが下がる
- 不整脈の分類がやさしく整理されている
- 初めて心電図を読む人向けの構成
-
2. 『読み方だけは確実に身につく心電図』 (著:米山 喜平)
👉 心電図が苦手な人でも「読むコツ」から理解できる定番の入門書。
洞不全症候群(SSS)についても章内で触れており、徐脈理解の基礎固めに最適。- 心電図の読み方が段階的に理解できる
- SSSなど徐脈性不整脈の前段階の理解に使える
- 受験生・新人医療者の基礎固めに最適
-
3. 『不整脈 知って解消 不安と疑問』(別冊NHKきょうの健康)
👉 一般読者向けの入門書で、不整脈全体をやさしく整理した内容。
洞不全症候群カテゴリーにも触れている可能性が高く、“まず知りたい”に適した構成。- 読みやすく、一般家庭向けにも最適
- 不整脈の全体像がとても理解しやすい
- 患者説明用としても活用できる
洞不全症候群・徐脈性不整脈の基礎を学ぶ入門書として特におすすめの3冊です。
■ 6. 治療:最も有名なのはペースメーカー
洞不全症候群は、薬だけで治せるケースは少ないのが特徴です。
治療の中心は ペースメーカー です。
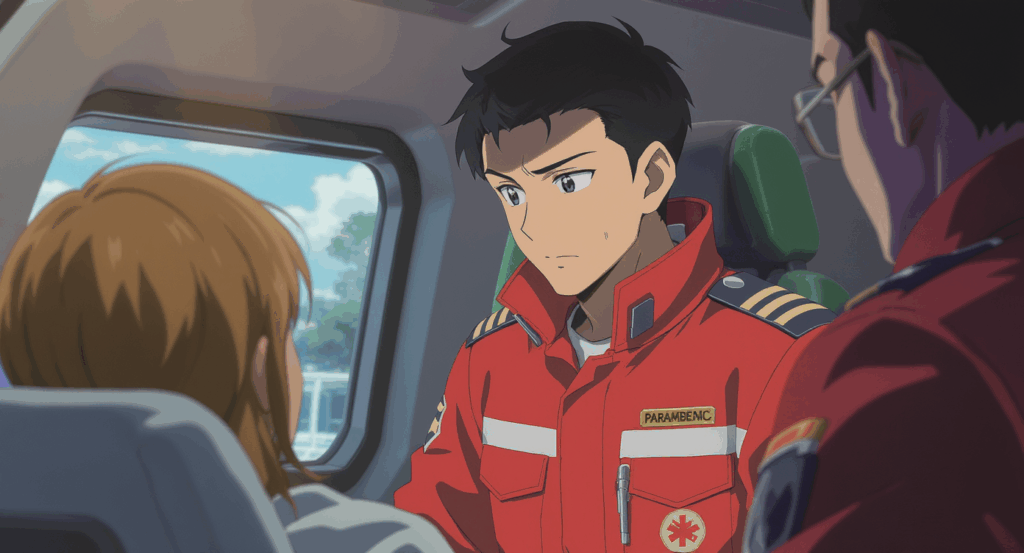
【治療の流れ】
● ① 原因となる薬の調整
まずは脈を抑える薬を中止または調整します。
● ② ペースメーカー植込み
症状がある場合、多くは植込みの適応になります。
ペースメーカーは簡単にいうと、
心臓の代わりに“規則正しい電気刺激”を送る装置 です。
皮膚の下に本体を入れ、リード(電線)を心臓へ通します。
▼ 植込み後のメリット
- 脈が止まるリスクがなくなる
- めまい・失神の改善
- 生活の質(QOL)が上がる
- 日常生活が安定する
手術は1〜2時間ほどで、体への負担も比較的小さく、
高齢者でも広く行われています。
● ③ 徐脈-頻脈症候群の場合
頻脈発作(心房細動など)がある人は、
ペースメーカー植込み+抗不整脈薬や抗凝固薬が必要になることがあります。
■ 7. 日常生活:ペースメーカー後の生活は?
基本的に、ペースメーカーを入れた後も
普段の生活はほとんど問題ありません。
▼ できること
- 入浴
- 運動(激しい接触スポーツ以外)
- 旅行
- スマホ・家電の使用
- 電車・飛行機の利用
▼ 注意するポイント
- 強い磁場(MRI対応機種ならOK)
- 金属探知機
- スマートフォンを本体から15cm離す
- 肩を大きく激しく動かす運動(術後1〜2ヶ月)
医師に具体的な活動レベルを相談しながら進めます。
■ 8. 放置するとどうなるのか?
治療しないまま放置すると、
洞不全症候群は命に関わる可能性があります。
▼ 放置した場合のリスク
- 突然の失神 → 転倒・外傷
- 脳への血流不足による認知機能低下
- 生命に危険を及ぼす徐脈
- 頻脈を合併すると心不全の進行
特に 徐脈-頻脈症候群 は重症化しやすく、
早めの治療が非常に重要です。
■ 9. 救急の現場ではどう対応する?
救急隊員・救急救命士の視点でも洞不全症候群は重要です。
▼ 救急時のポイント
- 脈が極端に遅い(30回台〜)
- 意識障害
- めまい・失神
- ショック兆候
- 不整脈の既往(特に心房細動・ペースメーカー歴)
救急現場では
アトロピンの使用、多発する徐脈の観察、必要に応じて経皮ペーシング
が検討されます。
■ 10. まとめ:洞不全症候群は早期発見で人生が変わる
洞不全症候群は加齢とともに増える病気で、
放置すると失神や心不全など重大な結果を招く可能性があります。

しかし、適切な治療(特にペースメーカー)を行えば、
多くの人が普段通りの生活を取り戻せる ことが知られています。
長年のめまい、ふらつき、疲れやすさ、息切れなどがある場合は、
「年のせいだから」と放置せず、一度心電図を受けることが大切です。
他にも記事が読みたい方はこちら👉心筋梗塞とは?──原因・症状・治療・予防をわかりやすく解説
📚 心電図・不整脈の入門におすすめの書籍(Amazon対応版)
-
1. 『かげさんのイラストで学ぶ 心電図と不整脈めも』
👉 現役看護師「かげ」さんによる、イラスト多めの超入門書。
波形の“見え方”と“不整脈の理屈”がやさしく理解できます。
洞不全症候群など徐脈性不整脈の理解にもつながり、最初の一冊に最適。- 図が多く、心電図を学ぶハードルが下がる
- 不整脈の分類がやさしく整理されている
- 初めて心電図を読む人向けの構成
-
2. 『読み方だけは確実に身につく心電図』 (著:米山 喜平)
👉 心電図が苦手な人でも「読むコツ」から理解できる定番の入門書。
洞不全症候群(SSS)についても章内で触れており、徐脈理解の基礎固めに最適。- 心電図の読み方が段階的に理解できる
- SSSなど徐脈性不整脈の前段階の理解に使える
- 受験生・新人医療者の基礎固めに最適
-
3. 『不整脈 知って解消 不安と疑問』(別冊NHKきょうの健康)
👉 一般読者向けの入門書で、不整脈全体をやさしく整理した内容。
洞不全症候群カテゴリーにも触れている可能性が高く、“まず知りたい”に適した構成。- 読みやすく、一般家庭向けにも最適
- 不整脈の全体像がとても理解しやすい
- 患者説明用としても活用できる
洞不全症候群・徐脈性不整脈の基礎を学ぶ入門書として特におすすめの3冊です。