―阿南英明氏(日本救急医学会)講演内容を踏まえた最新トピック対応―
(参照記事:https://sp.m3.com/news/iryoishin/1306043)
■ はじめに

近年、日本の救急医療体制は大きな変革期を迎えています。特に2024〜2025年にかけて議論されているのが、
**「高齢者搬送の急増」「在宅・施設入所者の救急搬送問題」「救急医療の受け皿不足」「救急医療基本法(仮称)制定の必要性」**です。
これは社会問題であると同時に、救急救命士国家試験にも直結する重要ポイントです。
本記事では、最新の学会報告(阿南英明氏 講演 / m3記事)を踏まえながら、国家試験に出やすいポイントを「現場目線+一般読者にもわかりやすい説明」でまとめていきます。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉未成年の飲酒が絶えない理由とその危険性 — 国家試験にも出る「飲酒の医学と法律」
📚 心電図・不整脈の入門におすすめの書籍(Amazon対応版)
-
1. 『かげさんのイラストで学ぶ 心電図と不整脈めも』
👉 現役看護師「かげ」さんによる、イラスト多めの超入門書。
波形の“見え方”と“不整脈の理屈”がやさしく理解できます。
洞不全症候群など徐脈性不整脈の理解にもつながり、最初の一冊に最適。- 図が多く、心電図を学ぶハードルが下がる
- 不整脈の分類がやさしく整理されている
- 初めて心電図を読む人向けの構成
-
2. 『読み方だけは確実に身につく心電図』 (著:米山 喜平)
👉 心電図が苦手な人でも「読むコツ」から理解できる定番の入門書。
洞不全症候群(SSS)についても章内で触れており、徐脈理解の基礎固めに最適。- 心電図の読み方が段階的に理解できる
- SSSなど徐脈性不整脈の前段階の理解に使える
- 受験生・新人医療者の基礎固めに最適
-
3. 『不整脈 知って解消 不安と疑問』(別冊NHKきょうの健康)
👉 一般読者向けの入門書で、不整脈全体をやさしく整理した内容。
洞不全症候群カテゴリーにも触れている可能性が高く、“まず知りたい”に適した構成。- 読みやすく、一般家庭向けにも最適
- 不整脈の全体像がとても理解しやすい
- 患者説明用としても活用できる
洞不全症候群・徐脈性不整脈の基礎を学ぶ入門書として特におすすめの3冊です。
第1章:なぜ高齢者搬送が増え続けているのか
● 日本は世界でも前例のない超高齢社会
2025年には団塊の世代がすべて75歳以上になり、**「後期高齢者が人口の18%」**という世界に例のない状態に。
救急搬送の統計でも、搬送の約60%は65歳以上の高齢者とされています。
● 高齢者特有の搬送理由
- 転倒・骨折
- 心不全・不整脈
- 感染症
- 認知症の行動異常
- 在宅医療管理の悪化(脱水・低栄養など)
ここまでは国家試験でも定番ですが、
新しい論点は **「在宅・施設の増加との関係」**です。
第2章:在宅療養者・施設入所者が増えると何が起きるか
現在、在宅医療・介護施設の利用者が急増しており、救急要請の背景が大きく変わっています。
● 現場の深刻な問題
① 施設スタッフの医療判断ができない
- 「念のため搬送してほしい」
- 「いつもと違う」
- 「往診医が捕まらない」
医療判断が曖昧なまま救急要請されるケースが増加。 - ② 在宅医の受け皿が夜間に弱い
夜間・休日に往診医が来られず、救急要請に依存しやすい。
③ 受け入れ病院のミスマッチ
本来は初期〜二次医療レベルで対応できる症状でも、
高齢者という理由だけで三次病院が混雑するケースもあります。
阿南氏(横須賀共済病院)は「運用のミスマッチ」を強く指摘しています。
これは国家試験でも問われやすい現代的テーマです。
第3章:三次救急のひっ迫はなぜ起きる?
■ 1. 高齢者搬送そのものが多い
救急車の約6割が高齢者である以上、三次病院への負担は必然です。
■ 2. 初期〜二次の役割が曖昧化
在宅・施設の救急要請は、病態の重症度よりも「対応できる医療機関」が少ないという要因で三次救急へ流れてしまうのです。
■ 3. 医療資源の偏り
地域によっては、
- 在宅医療リソース不足
- 夜間救急診療所の機能低下
- 二次医療圏の受け皿不足
といった課題があります。
阿南氏は明確に「地域間格差」を課題として挙げています。
第4章:今、議論されている「救急医療基本法(仮称)」とは?
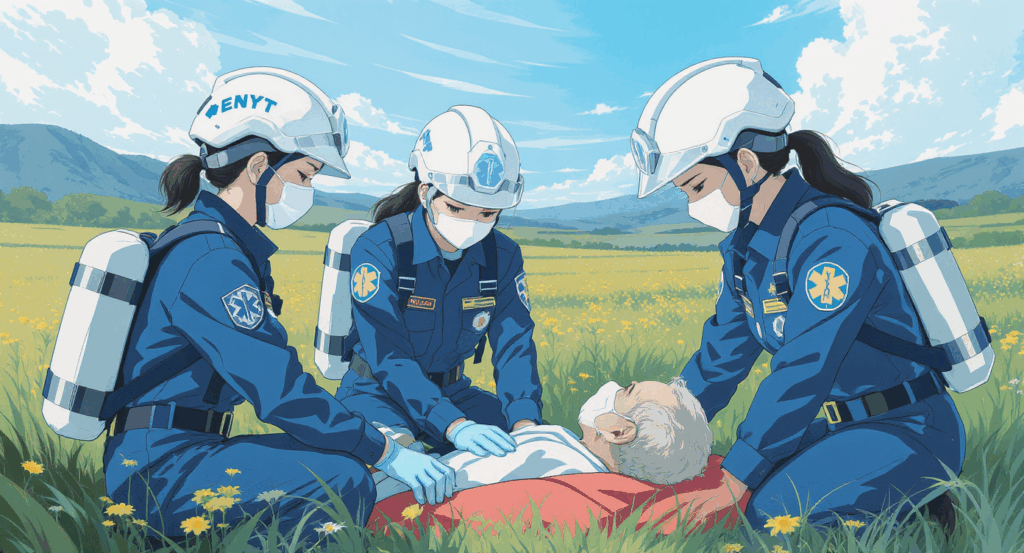
講演で特に強調されたのが、**「法的整備の必要性」**です。
● 現状の問題点
救急医療は主に行政通知レベルで運用されており、法律としての明文化がありません。
→ だからこそ、
- 役割の範囲
- 受け皿の種類
- 在宅・施設患者の扱い
が地域でバラつきやすく、救急隊にも負担がかかる。
● 新法の目的(案)
- 在宅・施設入所者を“救急医療の対象”として明記
- 初期・二次・三次の役割分担を明確化
- 受け皿の法的根拠
- 地域医療構想との連携
- 救急隊の搬送ルールが標準化
国家試験対策として押さえるべきは、
🔍 「救急医療の三本柱」
- 初期救急医療(軽症、外来中心)
- 二次救急医療(入院治療が必要)
- 三次救急医療(高度治療・救命救急センター)
これに
+「在宅・施設の受け皿」を明文化しようとしている
という最新トレンドです。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉未成年の飲酒が絶えない理由とその危険性 — 国家試験にも出る「飲酒の医学と法律」
📚 心電図・不整脈の入門におすすめの書籍(Amazon対応版)
-
1. 『かげさんのイラストで学ぶ 心電図と不整脈めも』
👉 現役看護師「かげ」さんによる、イラスト多めの超入門書。
波形の“見え方”と“不整脈の理屈”がやさしく理解できます。
洞不全症候群など徐脈性不整脈の理解にもつながり、最初の一冊に最適。- 図が多く、心電図を学ぶハードルが下がる
- 不整脈の分類がやさしく整理されている
- 初めて心電図を読む人向けの構成
-
2. 『読み方だけは確実に身につく心電図』 (著:米山 喜平)
👉 心電図が苦手な人でも「読むコツ」から理解できる定番の入門書。
洞不全症候群(SSS)についても章内で触れており、徐脈理解の基礎固めに最適。- 心電図の読み方が段階的に理解できる
- SSSなど徐脈性不整脈の前段階の理解に使える
- 受験生・新人医療者の基礎固めに最適
-
3. 『不整脈 知って解消 不安と疑問』(別冊NHKきょうの健康)
👉 一般読者向けの入門書で、不整脈全体をやさしく整理した内容。
洞不全症候群カテゴリーにも触れている可能性が高く、“まず知りたい”に適した構成。- 読みやすく、一般家庭向けにも最適
- 不整脈の全体像がとても理解しやすい
- 患者説明用としても活用できる
洞不全症候群・徐脈性不整脈の基礎を学ぶ入門書として特におすすめの3冊です。
第5章:国家試験に出るポイント(整理)
■ ① 日本の救急医療体制(初期・二次・三次)
→ 違い、役割、施設例は必出。
■ ② 高齢者搬送の増加と背景
- 超高齢社会
- 多疾患併存
- 在宅・施設利用者の増加
■ ③ 在宅・施設利用者に関する課題
- 医療判断の困難
- 夜間体制の弱さ
- 適切な受け皿不足
■ ④ 救急現場に求められるトリアージ
- 症状の重症度だけでなく
- **生活背景(在宅/施設)**を加味したトリアージが重要
■ ⑤ 救急搬送の適正化
- 三次救急のひっ迫
- 地域医療連携の仕組み
- 医療資源の問題
■ ⑥ 今後の制度化(救急医療基本法案)
→ ここを盛り込むことで、最新動向を踏まえた高得点の背景知識になる。
第6章:救急隊員として知っておくべきポイント
● 1. 在宅・施設での初期評価の重要性
- バイタル
- 観察
- 認知症の有無
- 日常との比較(ADL)
● 2. 搬送先の調整
- 地域の受け皿状況(在宅医、二次病院、救命センター)
- 重症度と搬送先の適合
● 3. 高齢者トリアージの難しさ
- 症状が非典型
- バイタルが正常でも重症のケースあり
(例:敗血症、心不全増悪、誤嚥性肺炎)
● 4. 地域によるルールの違い
→ 今後「法制化」により標準化が期待される。
第7章:まとめ

- 日本の救急医療は、高齢化により大きな構造変化の真っ只中。
- 在宅・施設利用者の増加は、救急要請の内容そのものを変えている。
- 受け皿問題、三次救急のひっ迫は、社会全体の医療体制の課題。
- 議論されている「救急医療基本法(仮称)」は、今後のスタンダードに。
- 国家試験では、従来の基礎知識+最新トピック理解が差になる。
今回のブログ記事の参照記事はこちら👉:https://sp.m3.com/news/iryoishin/1306043)
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉未成年の飲酒が絶えない理由とその危険性 — 国家試験にも出る「飲酒の医学と法律」
📚 心電図・不整脈の入門におすすめの書籍(Amazon対応版)
-
1. 『かげさんのイラストで学ぶ 心電図と不整脈めも』
👉 現役看護師「かげ」さんによる、イラスト多めの超入門書。
波形の“見え方”と“不整脈の理屈”がやさしく理解できます。
洞不全症候群など徐脈性不整脈の理解にもつながり、最初の一冊に最適。- 図が多く、心電図を学ぶハードルが下がる
- 不整脈の分類がやさしく整理されている
- 初めて心電図を読む人向けの構成
-
2. 『読み方だけは確実に身につく心電図』 (著:米山 喜平)
👉 心電図が苦手な人でも「読むコツ」から理解できる定番の入門書。
洞不全症候群(SSS)についても章内で触れており、徐脈理解の基礎固めに最適。- 心電図の読み方が段階的に理解できる
- SSSなど徐脈性不整脈の前段階の理解に使える
- 受験生・新人医療者の基礎固めに最適
-
3. 『不整脈 知って解消 不安と疑問』(別冊NHKきょうの健康)
👉 一般読者向けの入門書で、不整脈全体をやさしく整理した内容。
洞不全症候群カテゴリーにも触れている可能性が高く、“まず知りたい”に適した構成。- 読みやすく、一般家庭向けにも最適
- 不整脈の全体像がとても理解しやすい
- 患者説明用としても活用できる
洞不全症候群・徐脈性不整脈の基礎を学ぶ入門書として特におすすめの3冊です。


