迷走神経反射(Vasovagal Reflex)および迷走神経失神(Vasovagal Syncope)は、日常の様々な場面で比較的よく起こる「気絶」の代表的な原因です。
救急現場においても頻繁に遭遇するだけでなく、救急救命士国家試験においても毎年のように問われる重要なテーマです。
本記事では、一般の読者の方にも理解していただけるよう、また国家試験受験生にとっても得点源になるよう、迷走神経反射と迷走神経失神を 医学的背景・仕組み・症状・鑑別・現場での対応・予防方法 の観点から丁寧に解説いたします。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【完全版】神経系のしくみと働き──救急の現場で「人を読み解く力」が身につく、魂の神経学
📚 神経心理学・神経解剖を初学者から学ぶためのおすすめ書籍(Amazon対応版)
-
① 『初学者のための神経心理学入門』(松田 実 著)
👉 神経心理学・神経系の基礎を、症状・用語の背景も含めて丁寧に解説した入門書。
「神経の言葉が難しい」「全体像がつかみにくい」という初学者の壁を取り除いてくれます。- 神経解剖・神経生理・神経症状の理解を深める導入書
- 国家試験に出るポイントを基礎からつかむのに最適
- 一般読者でも読み進めやすい文章構成
-
② 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』(寺島 俊雄 著)
👉 難解になりがちな神経解剖学を「図解+講義ノート形式」で視覚的に理解できる定番書。
解剖が苦手な方や、“位置関係を図で覚えたい”学習スタイルの人に特に向いています。- 脳・脊髄・神経路のつながりが視覚的に理解できる
- 救急現場で「どこがどこにつながっているか」をイメージする力がつく
- 国家試験・現場教育の資料作成にも役立つ
神経心理学・神経解剖をやさしく、確実に理解したい初学者に最適な2冊です。
1. 迷走神経とは? ― 体を落ち着かせる神経
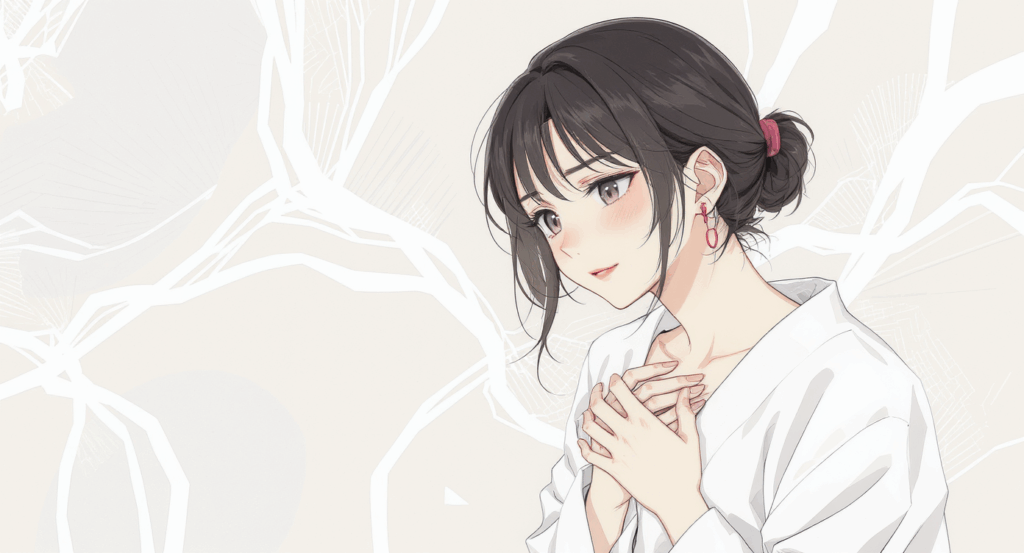
迷走神経(vagus nerve)は「副交感神経」の代表格であり、身体をリラックス状態へ導く働きがあります。
副交感神経は交感神経(“緊張” を作る神経)と対になり、体のバランスを整えています。
● 迷走神経の主な働き
- 心拍数を下げる
- 血圧を下げる(血管拡張作用)
- 胃腸の動きを促進する
- 気道を狭める
- 唾液分泌を増やす
つまり、迷走神経が刺激されすぎると 脈がゆっくりになり、血圧が下がる という状態になります。
この反応が強く出ることが 迷走神経反射 の基本的な仕組みです。
2. 迷走神経反射とは? ― 身体の「守りの反応」が強すぎた状態
迷走神経反射(Vasovagal Reflex)とは、何らかのストレスや痛み・精神的緊張により、迷走神経が急激に強く働く状態です。
● よくみられる誘因(非常に重要)
- 採血や注射の恐怖
- 血液を見たとき
- 急激な痛み
- 立ち続けている状態
- 脱水・空腹・睡眠不足
- 強い精神的ストレス
- 排便時のいきみ(排便失神)
これらの刺激により、副交感神経が一気に優位になると、
- 心拍数の急低下(徐脈)
- 血圧の低下(血管拡張)
- 脳への血流不足
が起こり、症状として現れてきます。
典型的には、
「顔面蒼白 → 冷や汗 → 吐き気 → 失神」
という流れで、救急現場でも頻繁に遭遇します。
3. 迷走神経失神とは? ― 迷走神経反射による“一時的な意識喪失”
迷走神経失神(Vasovagal Syncope)は、迷走神経反射によって引き起こされる 一過性の意識消失 です。
脳への血流が一時的に低下することで、短時間の気絶が起こります。
大半は短時間で回復しますが、倒れ方によっては外傷を伴うことがあり、救急の現場では注意が必要です。
● 発症の典型的な流れ
- 痛み・恐怖・ストレス・脱水などの誘因
- 迷走神経が急激に刺激される
- 血圧低下・徐脈
- 脳血流不足
- 意識消失
- すぐに回復するが、倦怠感がしばらく残ることもある
4. 前兆症状 ― 迷走神経失神の最大の特徴
迷走神経失神には、他の危険な失神とは違って「前兆」があることが非常に重要です。
国家試験でも頻出ポイントとなります。
● 前駆症状(非常に典型)
- めまい
- 耳鳴り
- 目の前が暗くなる
- 手足のしびれ
- 冷や汗
- 悪心(吐き気)
- あくびが出る
- 顔面蒼白
- 動悸(初期)
これらの症状が出た時点で、横になる・水分を摂るなどの対策を行えば失神を防げることがあります。
5. 失神後の状態 ― 回復は速いが油断は禁物
迷走神経失神は、倒れて頭の位置が低くなることで脳血流が回復しやすく、意識が速く戻るのが特徴です。
● 失神後の典型
- 数秒~1分程度で意識が戻る
- しばらく倦怠感・悪心が残る
- 再発の可能性がある(同じ刺激で再燃しやすい)
📚 神経心理学・神経解剖を初学者から学ぶためのおすすめ書籍(Amazon対応版)
-
① 『初学者のための神経心理学入門』(松田 実 著)
👉 神経心理学・神経系の基礎を、症状・用語の背景も含めて丁寧に解説した入門書。
「神経の言葉が難しい」「全体像がつかみにくい」という初学者の壁を取り除いてくれます。- 神経解剖・神経生理・神経症状の理解を深める導入書
- 国家試験に出るポイントを基礎からつかむのに最適
- 一般読者でも読み進めやすい文章構成
-
② 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』(寺島 俊雄 著)
👉 難解になりがちな神経解剖学を「図解+講義ノート形式」で視覚的に理解できる定番書。
解剖が苦手な方や、“位置関係を図で覚えたい”学習スタイルの人に特に向いています。- 脳・脊髄・神経路のつながりが視覚的に理解できる
- 救急現場で「どこがどこにつながっているか」をイメージする力がつく
- 国家試験・現場教育の資料作成にも役立つ
神経心理学・神経解剖をやさしく、確実に理解したい初学者に最適な2冊です。
6. 鑑別すべき危険な失神 ― 国家試験の超頻出ポイント
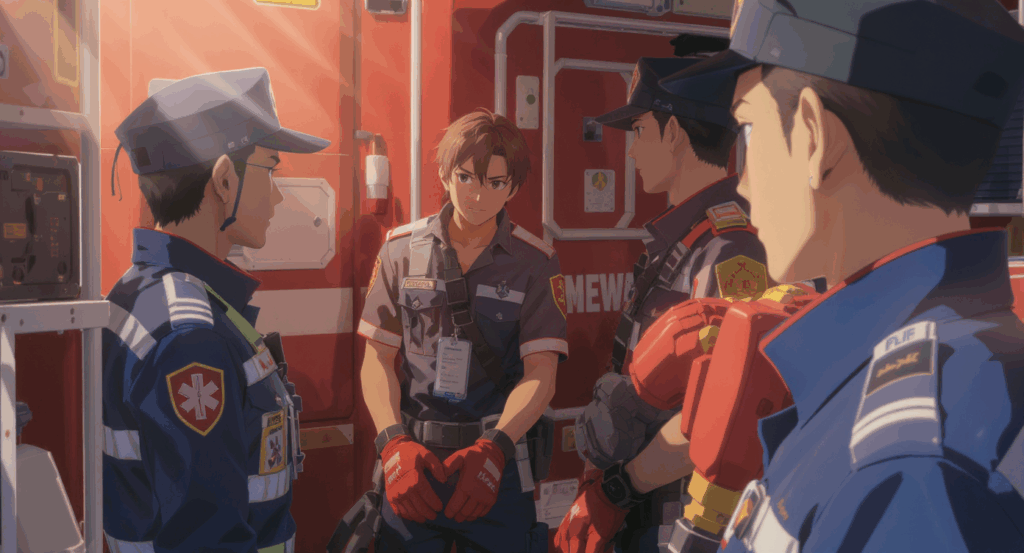
失神はすべてが良性というわけではありません。
迷走神経失神と見た目が似ていても、命に関わる疾患が隠れていることがあります。
● 鑑別が必要な「危険な失神」
| 疾患 | 特徴 |
| 心原性失神(不整脈) | 前兆がない・突然倒れる・すぐ戻らない |
| 大動脈弁狭窄症 | 労作時の失神 |
| 肥大型心筋症 | 若年でもあり得る・運動時 |
| 肺血栓塞栓症 | 呼吸困難を伴う |
| 低血糖 | 発汗・意識障害が長い |
| 脳卒中 | 片麻痺・構音障害など随伴症状あり |
国家試験では、
“前兆がある失神 → 迷走神経失神の可能性が高い”
と覚えておくと得点につながります。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【完全版】神経系のしくみと働き──救急の現場で「人を読み解く力」が身につく、魂の神経学
7. 発生のメカニズム(深掘り) ― 国家試験対策にも必須
迷走神経反射のメカニズムは “副交感神経の過剰反射” が中心ですが、もう少し深く見てみましょう。
● ① 心臓の機械受容器が誤作動する
精神的ストレスや痛みによって、
心臓の受容器が「血圧が上がりすぎた」と誤って判断します。
● ② 中枢で副交感神経が強く優位に
その結果、副交感神経が急激に刺激され、交感神経は抑制されます。
● ③ 徐脈+血管拡張 → 血圧低下
- 心拍数低下(徐脈)
- 血管拡張による血圧低下
この2つが同時に起こることが 脳血流低下 → 失神 の原因となります。
● この反射を「ベゾルド–ヤーリッシュ反射」と呼ぶ
国家試験に出ることがあります。
8. 救急現場での対応 ― 最も重要なのは“姿勢”
迷走神経失神の多くは、適切な対応で重症化を避けられます。
● ① 安全確保・転倒防止
倒れると頭部外傷などにつながるため、
前兆を感じた時点で “横になること” が最も重要です。
● ② 体位
- 仰臥位(横になる)
- 足を軽く挙上(下肢挙上位)
これにより、脳への血流が早期に改善します。
● ③ バイタルサインの確認
- 徐脈の有無
- 血圧の低下
- SpO₂
- 意識の改善状況
● ④ 外傷のチェック
倒れた際に頭を打っている可能性があり要注意です。
● ⑤ 水分補給(脱水が疑われる場合)
経口摂取が可能であれば効果的です。
● ⑥ 救急要請が必要なケース
- 意識がなかなか戻らない
- 胸痛や息苦しさを伴う
- 頭部を強く打っている
- 初めての失神で原因不明
- 心疾患の既往がある
- 高齢者や妊婦の場合
9. 予防方法 ― 誘因を避ければ多くは防げる
迷走神経反射は、誘因を知れば予防できる場合が多いです。
● 予防のポイント
- 脱水を避け、こまめに水分補給する
- 長時間の立位を避ける
- 採血・注射前に深呼吸を行う
- 朝の急な立ち上がりを避ける
- 不安が強い場合は座った姿勢で処置を受ける
- 食事を抜かない(低血糖防止)
特に国家試験では、
「誘因 → 血管迷走神経反射 → 徐脈 → 失神」
という流れを理解することが重要です。
10. 国家試験のまとめポイント
以下は試験に非常に出やすい内容です。
- 迷走神経失神は 前駆症状 がある
- 失神後は速やかに回復する
- 誘因は「痛み・恐怖・脱水・長時間立位」
- 徐脈・血圧低下が起こる
- ベゾルド–ヤーリッシュ反射が関与
- 鑑別すべきは心原性失神(前兆なし・突然)
11. 一般の方へのまとめ
迷走神経失神は命に関わることはほとんどありませんが、
“転倒による怪我” がもっとも大きなリスクです。
そのため、
- 前兆を感じたらすぐ座る・横になる
- 水分を摂る
- 無理をしない
これらを意識していただくことで予防につながります。
12. まとめ
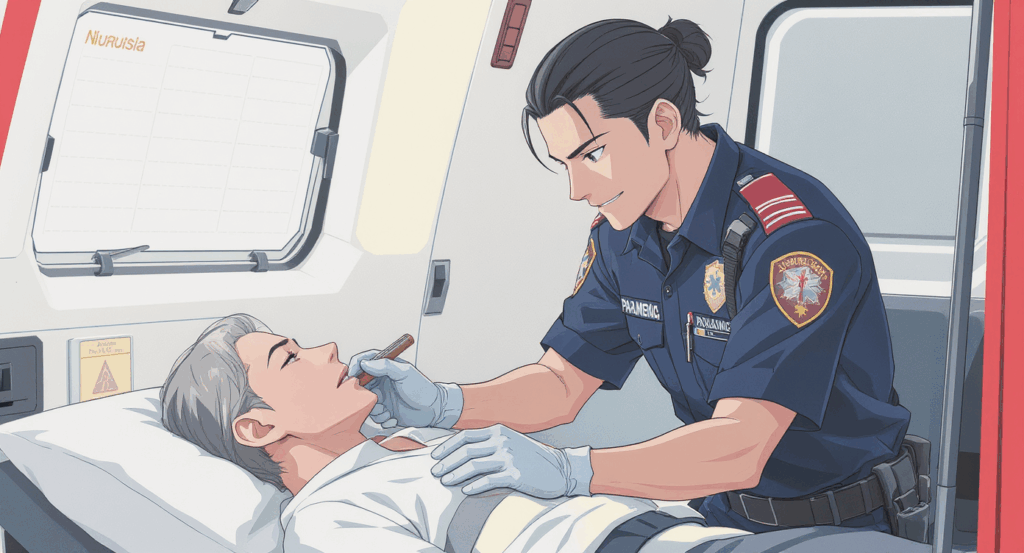
迷走神経反射と迷走神経失神は、多くの人が経験し得る一般的な症状でありながら、
救急現場ではきちんと鑑別すべき重要なテーマです。
国家試験の出題頻度も高く、正確な知識が必要になります。
- 迷走神経が過剰に働くことにより、血圧と脈拍が低下
- 誘因は痛み・恐怖・脱水など
- 前兆を察知すれば予防可能
- 危険な失神(心原性など)との鑑別が重要
- 救急対応は “体位の確保” が最優先
迷走神経失神は正しく理解すれば怖いものではありません。
知っておくことで、ご自身や周囲の安全確保に役立ちます。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【完全版】神経系のしくみと働き──救急の現場で「人を読み解く力」が身につく、魂の神経学
📚 神経心理学・神経解剖を初学者から学ぶためのおすすめ書籍(Amazon対応版)
-
① 『初学者のための神経心理学入門』(松田 実 著)
👉 神経心理学・神経系の基礎を、症状・用語の背景も含めて丁寧に解説した入門書。
「神経の言葉が難しい」「全体像がつかみにくい」という初学者の壁を取り除いてくれます。- 神経解剖・神経生理・神経症状の理解を深める導入書
- 国家試験に出るポイントを基礎からつかむのに最適
- 一般読者でも読み進めやすい文章構成
-
② 『カラー図解 神経解剖学講義ノート』(寺島 俊雄 著)
👉 難解になりがちな神経解剖学を「図解+講義ノート形式」で視覚的に理解できる定番書。
解剖が苦手な方や、“位置関係を図で覚えたい”学習スタイルの人に特に向いています。- 脳・脊髄・神経路のつながりが視覚的に理解できる
- 救急現場で「どこがどこにつながっているか」をイメージする力がつく
- 国家試験・現場教育の資料作成にも役立つ
神経心理学・神経解剖をやさしく、確実に理解したい初学者に最適な2冊です。


