便利さの一方で“37%が不安視する個人情報リスク”と今後の課題
■ はじめに
2025年12月2日より、これまで使用してきた「紙の健康保険証」は新規発行が終了し、マイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」へ全面的に移行することが決定しております。
Yahoo!記事はこちら👉【マイナ保険証一本化】便利さは感じるが…個人情報の不安37%が示す“マイナ保険証の課題”(スマホライフPLUS) #Yahooニュース
この制度は、国が推進する「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」の中核として位置づけられており、
・医療機関の受付がスムーズになる
・薬剤情報や健診情報の共有が可能となる
・転職や引っ越し後の保険証切り替えが迅速になる
など、利便性の向上が期待されています。
しかしその一方で、国民の約37%が「個人情報の取り扱いに不安を感じる」と回答しており、制度への信頼性や理解の浸透には課題も残されています。
本記事では、制度の仕組みや利点はもちろん、
- なぜ不安の声が多いのか
- 医療現場ではどのような課題があるのか
- 救急隊・医療従事者が押さえるべきポイントはどこか
- 一般の方が安心して利用するためには何が必要か
- 医療DXの未来予測
といった内容を詳しく解説いたします。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【やさしく解説】生活保護制度とは?
📚参考図書(救急救命士・医療学生におすすめ)
-
『救急救命士標準テキスト 改訂第11版』へるす出版
国家試験対策の定番。酸素飽和度・換気・循環評価など、モニタリングの基本が体系的に学べます。
➡️ Amazonで見る -
『イラストで解る 救急救命士国家試験直前ドリル 第4版』
国試過去問と出題傾向を分析したドリル。
➡️ Amazonで見る -
病気がみえる vol.5 血液 第3版
文字より“ビジュアル”で覚える。血液疾患の理解が劇的に変わる1冊。
➡️ Amazonで見る -
『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン2022〔第6版〕』日本呼吸器学会
呼吸生理と酸素療法の最新知見を網羅。慢性呼吸不全や在宅酸素療法を理解するうえで必読の一冊。
➡️ Amazonで見る
1. マイナ保険証一本化の背景
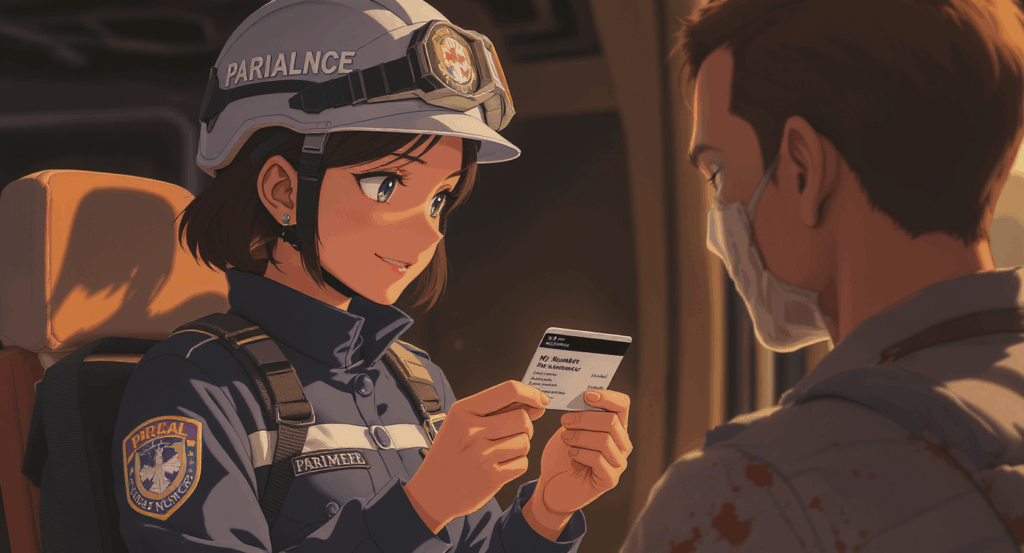
健康保険証の一本化は、「カードの変更」という表面的な話に留まりません。実際には、医療情報のデジタル化を大きく進めるための基盤整備であり、より安全で効率的な医療提供体制を作るための重要な政策です。
1-1. 医療DXの推進とマイナ保険証
政府が取り組む医療DXは、次の要素で構成されています。
- オンライン資格確認の義務化
- 電子処方箋の普及
- 電子カルテ情報の標準化
- 医療機関間のデータ連携
- 救急搬送時の医療情報共有の強化
これらを実現するには、国民全員が共通して利用できる「本人確認手段」が不可欠であり、その役割を担うのがマイナ保険証です。
1-2. なぜ紙の保険証は廃止されるのか
紙の健康保険証は、以下の問題点を抱えていました。
- 切り替えのたびに郵送や発行の手間がある
- 有効期限や資格情報の反映に時間がかかる
- 不正利用のリスクがある
- 医療機関での確認作業が煩雑
マイナ保険証は、これらの課題を解決するための手段であり、より正確かつ迅速な資格確認を可能にします。
2. マイナ保険証のメリット
制度の利点を、「利用者」「医療機関」「社会全体」という三つの視点から見てまいります。
2-1. 利用者にとってのメリット
■ 1枚のカードですべてが完結
マイナンバーカードさえあれば、健康保険証としても利用でき、カード類の管理が簡素化されます。
■ 転職・引っ越し後のトラブルが少なくなる
これまで頻繁に発生していた、
「保険証が届いていないため受診できない」
といった問題が軽減されます。
■ 医療情報の共有が可能
薬剤情報や健診結果が医療機関同士で共有できるようになるため、重複投薬の防止など医療安全の向上に繋がります。
2-2. 医療機関にとってのメリット
■ 受付の負担が軽減
オンライン資格確認が可能となることで、窓口業務が効率化されます。
■ 最新の資格情報を参照できる
紙の保険証のように「無効」「期限切れ」といったトラブルが減少します。
2-3. 社会全体にとってのメリット
- 医療費の無駄が減り、制度の持続可能性が高まる
- 医療情報が研究などにも活用しやすくなる
3. それでも37%が「不安」と回答した理由
利便性は理解されつつも、不安が生じる理由は複数あります。
3-1. 個人情報漏えいの懸念
1枚のカードに多くの情報が紐づくため、
「紛失したら悪用されるのではないか」
「ICチップを読み取られるのでは」
といった不安が生じやすくなります。
政府は強固な暗号化を施していると説明していますが、一般の方に十分な説明が届いていないことが課題です。
3-2. 過去の登録ミス・運用トラブル
制度開始当初に、情報の紐付けミスや機器トラブルが報道されました。
こうした事例が不信感を生んでいます。
3-3. 情報が「どこまで共有されるのか」が分かりにくい
薬剤情報・健診情報・医療データの扱われ方が明確に理解されていないため、不安につながっています。
3-4. デジタル環境の格差
高齢者やスマホに不慣れな方が置いていかれない設計が求められています。
4. 救急現場から見た制度の課題
救急隊や医療従事者の視点からは、制度の実際の運用における課題がより明確です。
4-1. 患者がカードを携帯していないことが多い
救急搬送の現場では、
財布や身分証を持参できない状態の患者が非常に多く、マイナ保険証の利用が難しい現状があります。
4-2. 医療機関によって読み取り機器が整備されていない
特に小規模の医療機関や歯科では、導入が遅れているケースもあり、制度を十分に活用できない場面が見られます。
4-3. オンライン資格確認の遅延
回線トラブルや機器の不具合により、受付が滞ることがあります。
4-4. 救急現場ではアナログ情報が最も重要
現場で迅速性を求められる救急医療では、
- お薬手帳
- 家族からの情報
- 患者の所持品
など、従来のアナログ情報が依然として最も役立っています。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【やさしく解説】生活保護制度とは?
Yahoo!記事はこちら👉【マイナ保険証一本化】便利さは感じるが…個人情報の不安37%が示す“マイナ保険証の課題”(スマホライフPLUS) #Yahooニュース
📚参考図書(救急救命士・医療学生におすすめ)
-
『救急救命士標準テキスト 改訂第11版』へるす出版
国家試験対策の定番。酸素飽和度・換気・循環評価など、モニタリングの基本が体系的に学べます。
➡️ Amazonで見る -
『イラストで解る 救急救命士国家試験直前ドリル 第4版』
国試過去問と出題傾向を分析したドリル。
➡️ Amazonで見る -
病気がみえる vol.5 血液 第3版
文字より“ビジュアル”で覚える。血液疾患の理解が劇的に変わる1冊。
➡️ Amazonで見る -
『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン2022〔第6版〕』日本呼吸器学会
呼吸生理と酸素療法の最新知見を網羅。慢性呼吸不全や在宅酸素療法を理解するうえで必読の一冊。
➡️ Amazonで見る
5. マイナ保険証は単体では不十分
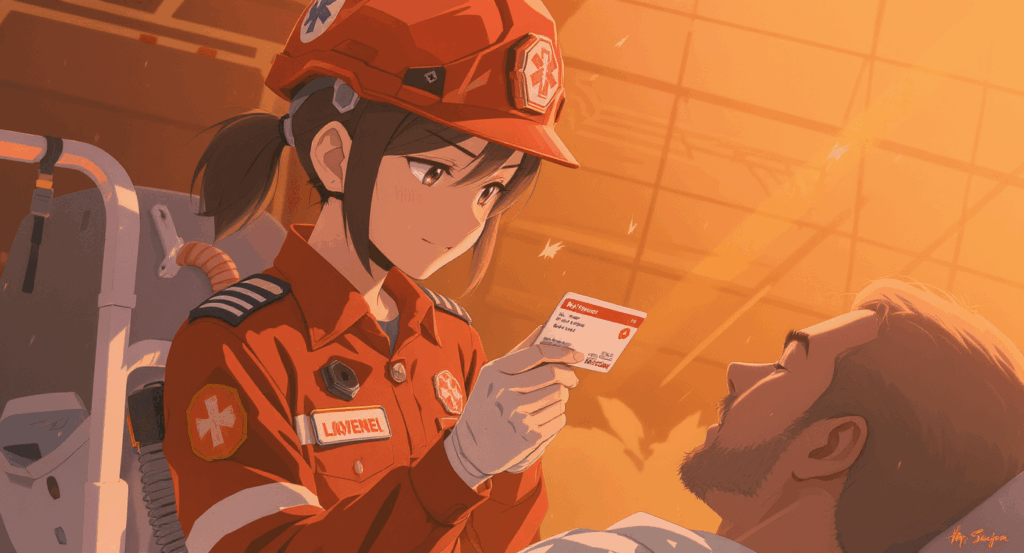
本来の価値は、医療DXの他の施策と組み合わさって初めて発揮されます。
5-1. 電子処方箋との連携
薬剤の重複や併用禁忌のチェックが容易になります。
5-2. 電子カルテ標準化との連動
どの医療機関でも患者情報を共有できる未来が目標とされています。
5-3. 救急医療でのリアルタイム情報共有
将来的には、救急隊が患者情報を即時に確認できる仕組みの構築が予定されています。
6. 不安を解消するための3つの方法
一般の方が安心して制度を利用するために有効な方法をご紹介します。
6-1. マイナポータルで情報提供の履歴を確認する
自分の医療情報が「いつ・どこで・誰に」参照されたかを確認できます。
6-2. 紛失時は24時間いつでもカード停止が可能
オンラインで迅速に停止できるため、悪用を防止できます。
6-3. 普段は携帯しなくても問題はない
必要な時だけ持参すればよく、「常に持ち歩かなければならない」という誤解を解くことが重要です。
7. 制度改善のために必要なこと
今後の課題として、次の4点が挙げられます。
- 情報の透明性向上
- デジタル弱者への支援拡充
- 機器整備の加速
- 緊急時の例外運用の整備
8. 国家試験対策としての要点
医療系国家試験では次の点が問われる可能性があります。
- マイナ保険証とオンライン資格確認の仕組み
- 医療情報共有には「本人同意」が必須
- 電子処方箋と医療DXの位置付け
- 健康保険証の廃止時期
9. 今後の展望:スマホ保険証の時代へ
マイナンバーカードだけでなく、スマホを利用した「デジタル保険証」の実現が進められています。
今後はスマホアプリで資格確認が完結し、より便利な受診環境が整っていくと予測されます。
■ まとめ
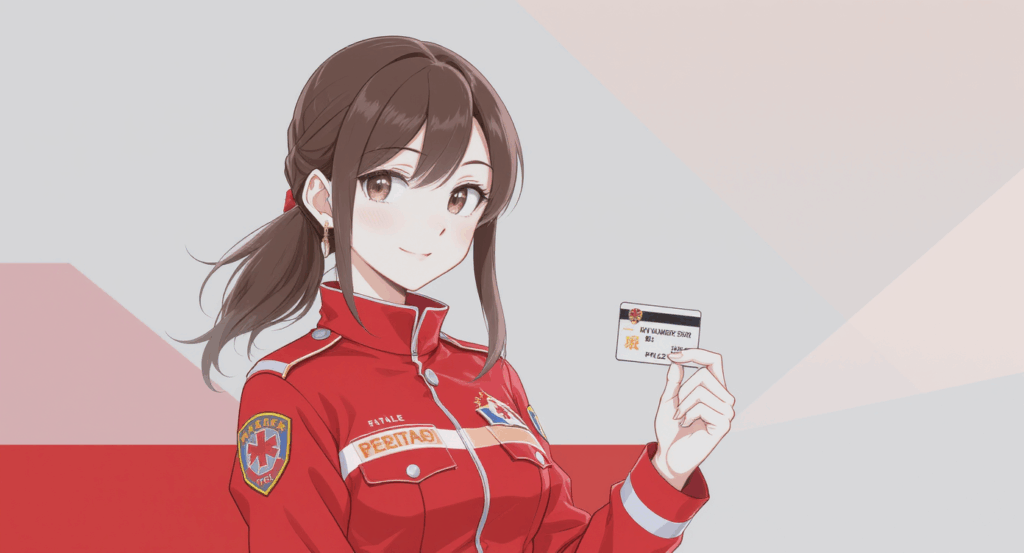
マイナ保険証一本化は、医療の利便性向上や安全性向上につながる重要な制度である一方で、個人情報の取り扱いへの不安や制度運用上の課題も存在しています。
大切なのは、
利便性と不安の双方を正しく理解し、制度を賢く利用していく姿勢です。
また、医療従事者や救急隊の立場からは、制度のメリットだけでなく、
「現場で起きる実務上の問題」
を把握したうえで柔軟に対応していくことが求められます。
制度が改良され、医療DXがより進展することで、日本の医療の安全性と効率性は確実に向上していくでしょう。
もっと医療情報を知りたい方はこちら👉【やさしく解説】生活保護制度とは?
Yahoo!記事はこちら👉【マイナ保険証一本化】便利さは感じるが…個人情報の不安37%が示す“マイナ保険証の課題”(スマホライフPLUS) #Yahooニュース
📚参考図書(救急救命士・医療学生におすすめ)
-
『救急救命士標準テキスト 改訂第11版』へるす出版
国家試験対策の定番。酸素飽和度・換気・循環評価など、モニタリングの基本が体系的に学べます。
➡️ Amazonで見る -
『イラストで解る 救急救命士国家試験直前ドリル 第4版』
国試過去問と出題傾向を分析したドリル。
➡️ Amazonで見る -
病気がみえる vol.5 血液 第3版
文字より“ビジュアル”で覚える。血液疾患の理解が劇的に変わる1冊。
➡️ Amazonで見る -
『COPD(慢性閉塞性肺疾患)診断と治療のためのガイドライン2022〔第6版〕』日本呼吸器学会
呼吸生理と酸素療法の最新知見を網羅。慢性呼吸不全や在宅酸素療法を理解するうえで必読の一冊。
➡️ Amazonで見る


