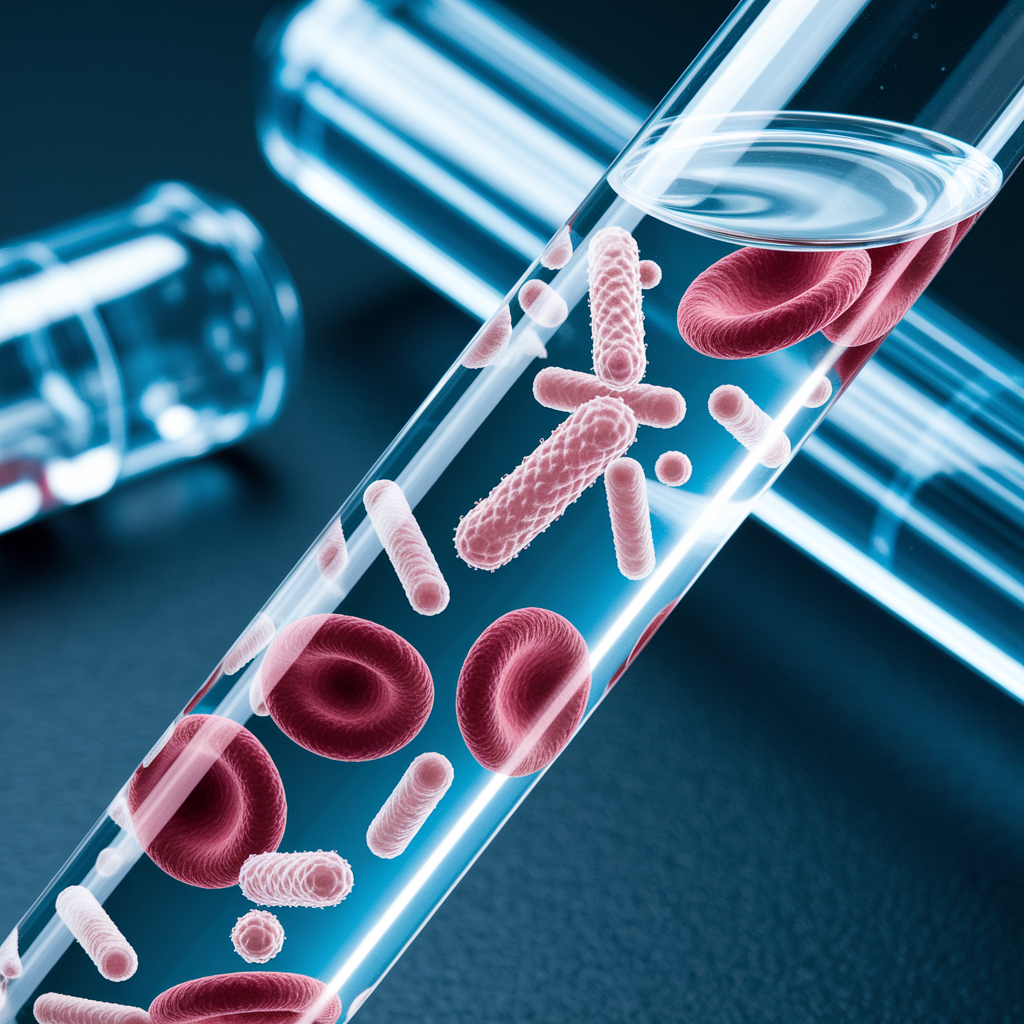こんにちは!今回は救急救命士国家試験で頻出の「体液」について、重要ポイントを図解とともにわかりやすくまとめてみました。体液の分類からホルモンによる調節、そして脱水や浮腫などの病態まで、この1記事で一気に復習しましょう!
🔍 体液の分類と構成割合
人の体の約60%は水分でできています。この水分=「体液」は、以下のように分類されます。
- 細胞内液(ICF):全体の約2/3を占め、細胞の中に存在
- 細胞外液(ECF):残りの1/3で、血漿や間質液など
- 血漿と間質液の割合:ECFのうち、血漿は約1/4、間質液は約3/4
⚡ 電解質の分布と役割
体液内に含まれる電解質は、部位によって分布が異なります。
| イオン | 細胞内液 | 細胞外液 |
| Na⁺ | 少ない | 多い |
| K⁺ | 多い | 少ない |
| Cl⁻ | 少ない | 多い |
| HCO₃⁻ | 少ない | 多い |
この分布が崩れると、神経・筋の機能に大きな影響が出ます。試験ではK⁺やNa⁺の異常と症状の関連を問われることが多いです。
🔄 ホルモンによる体液の調節機構
体液の量や濃度は、いくつかのホルモンによって絶妙にコントロールされています。
- ADH(抗利尿ホルモン):水の再吸収を促進し、尿量を減らす
- アルドステロン:Na⁺の再吸収とK⁺の排泄を促進
- ANP(心房性ナトリウム利尿ペプチド):Na⁺の排泄を促進し、体液量を調整
⚠ 体液異常とその症状
試験では以下のような体液異常とその対応が問われます。
| 異常 | 原因 | 症状 | 処置 |
| 脱水 | 発汗・嘔吐・出血 | 口渇、頻脈、意識障害 | 補液(等張液) |
| 浮腫 | 心不全、腎不全 | むくみ、体重増加 | 利尿薬など |
| 高Na血症 | 水分摂取不足 | 錯乱、痙攣 | 低張液補正 |
| 低Na血症 | SIADH、水中毒 | 頭痛、痙攣 | 水制限、Na補正 |
✅ まとめ:ここを押さえよう!
- 体液は細胞内と細胞外に分かれ、それぞれの割合と内容が違う
- 電解質のバランスが崩れると症状が出る
- ホルモンが体液の調節に重要な役割を果たす
- 異常時の臨床症状と対応はセットで覚える!
国家試験では、こうした知識が組み合わさった応用問題がよく出題されます。図表と一緒に覚えて、しっかり対策していきましょう!
問題演習:体液に関する国家試験対策問題
【第1問】
成人において、体重の約60%を占める体液のうち、細胞内液が占める割合はどれか?
A. 約1/4
B. 約1/3
C. 約2/3
D. 約3/4
正解:C
🗒️解説:体液のうち約2/3が細胞内液(ICF)で、残りの1/3が細胞外液(ECF)です。
【第2問】
細胞外液に多く含まれる電解質はどれか?
A. カリウム(K⁺)
B. マグネシウム(Mg²⁺)
C. ナトリウム(Na⁺)
D. リン酸(PO₄³⁻)
正解:C
🗒️解説:ナトリウムは細胞外液に多く、カリウムは細胞内液に多く含まれます。
【第3問】
抗利尿ホルモン(ADH)の主な作用として正しいのはどれか?
A. Na⁺の再吸収を促進する
B. K⁺の排泄を促進する
C. 水の再吸収を促進する
D. Na⁺の排泄を促進する
正解:C
🗒️解説:ADHは腎集合管に作用して水の再吸収を促進し、体液量を維持します。
【第4問】
SIADHによって起こりやすい電解質異常はどれか?
A. 高ナトリウム血症
B. 低ナトリウム血症
C. 高カリウム血症
D. 低カリウム血症
正解:B
🗒️解説:SIADHではADHが過剰に分泌されるため水が過剰に再吸収され、相対的にNa⁺濃度が低下します。
【第5問】
次のうち、体液量の増加(浮腫)を引き起こす疾患として誤っているものはどれか?
A. 心不全
B. 腎不全
C. 低アルブミン血症
D. 糖尿病
正解:D
🗒️解説:糖尿病は高血糖による脱水の原因になりやすく、体液量の増加とは逆の作用になります。
📌 ワンポイントアドバイス
問題を解くときは、「どこにどんな体液がどれだけあるか?」「どのイオンがどこに多いか?」「調節しているホルモンは何か?」を意識すると正答率が上がります!